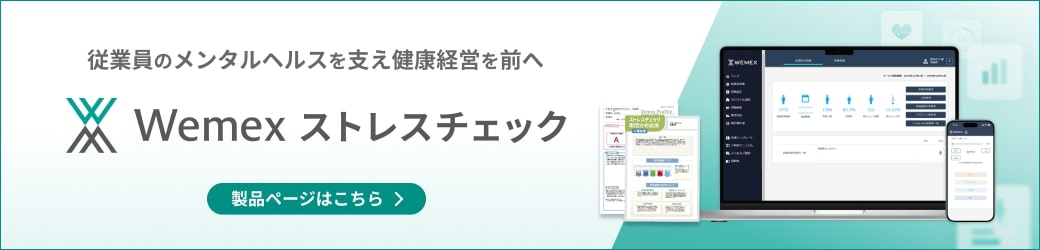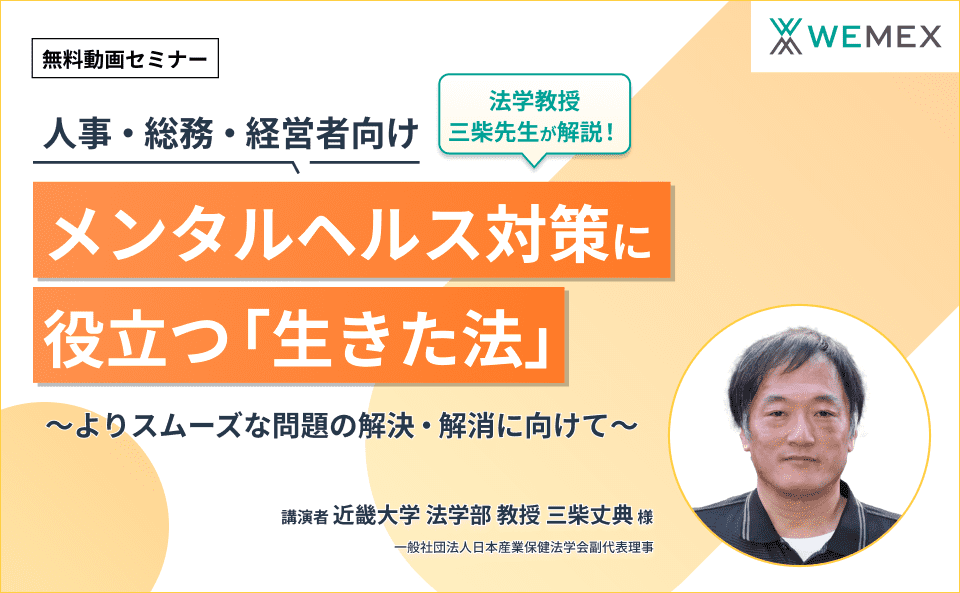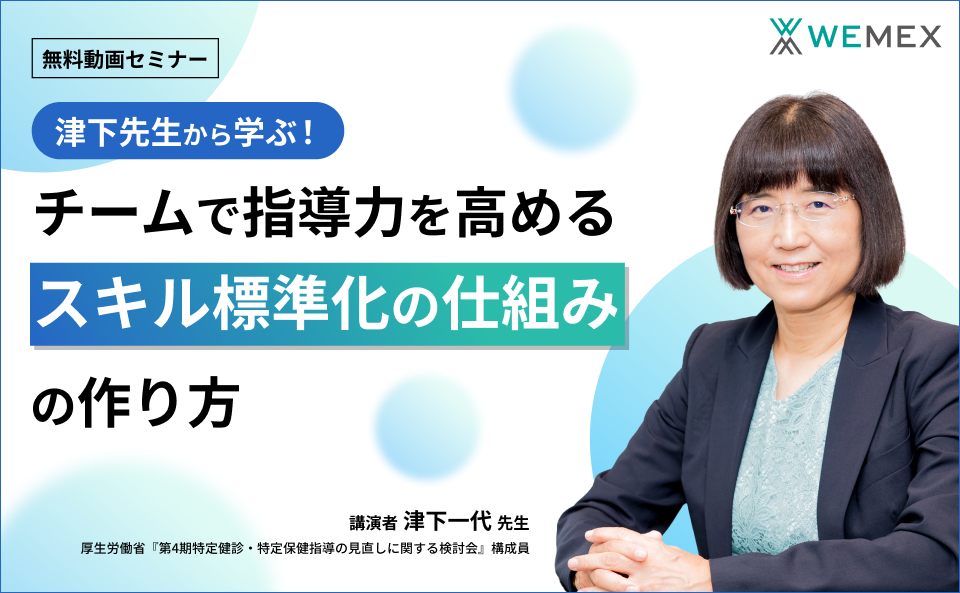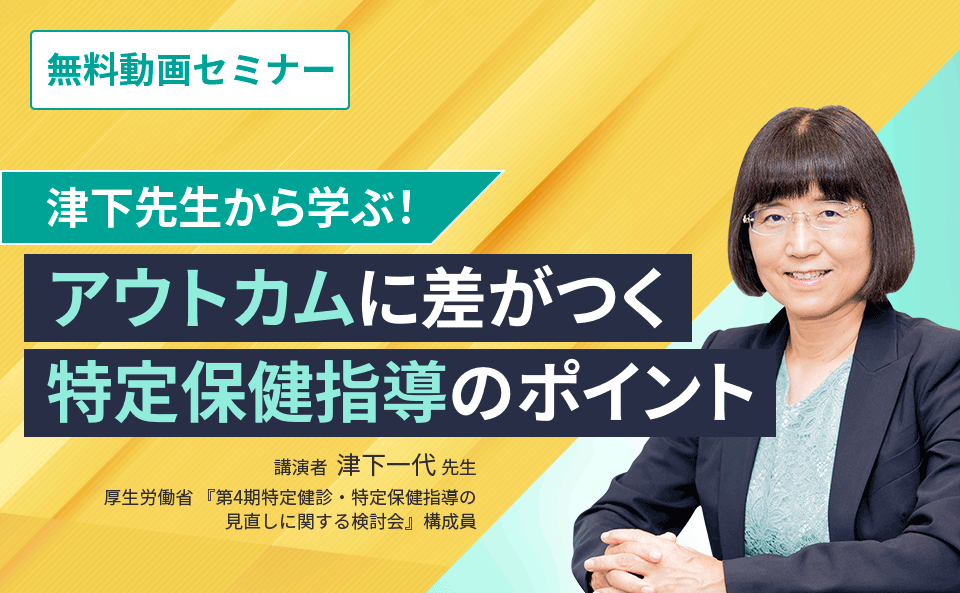目次
健康経営優良法人とは

健康経営優良法人とは、健康経営®を実践する企業を「見える化」する制度です。2016年から、経済産業省と日本健康会議によって実施されています。認定を受けたい企業が申請を行うと評価が行われ、その結果が公表される仕組みです。
また、健康経営優良法人の認定は従業員数に応じて、大規模法人部門と中小規模法人部門に分かれています。いずれの部門でも、認定を受けた企業は健康経営優良法人のロゴをホームページなどに掲載することができます。
関連記事:健康経営とは?メリットや取り組み方を解説
大規模法人部門
大規模法人部門の対象となる従業員数は次の通りです。
・製造業その他:301人以上
・サービス業・卸売業:101人以上
・小売業:51人以上
2025年度は3,400法人が大規模法人部門で認定されています。また、認定法人のうち上位500社には「ホワイト500」の称号が付与されます。ホワイト500認定企業は、通常の健康経営優良法人ロゴの下に「ホワイト500」と記載されたロゴを使用できます。
中小規模法人部門
中小規模法人部門は、従業員数が上記より少ない企業を対象としています。基準は次の通りです。
・製造業その他:1人以上300人以下
・サービス業・卸売業:1人以上100人以下
・小売業:1人以上50人以下
2025年度は19,796法人が中小規模法人部門で認定されています。このうち上位500社には「ブライト500」、さらに501~1,500位には「ネクストブライト1000」の称号が付与されます。認定企業はそれぞれの称号入りロゴをホームページなどに掲載できます。
健康経営優良法人の認定を受けるメリット
昨今、多くの企業が健康経営優良法人の認定取得を目指して健康経営に取り組んでいます。では、認定を受けることでどのようなメリットがあるのでしょうか。
企業イメージの向上
健康経営優良法人として認定を受けている企業は、従業員を大切にしている印象を与えます。求職者にとって「ホワイト企業」と認識され、採用活動にも有利に作用します。また、消費者や株主、地域社会からもポジティブな評価を得られるため、企業の長期的成長に寄与します。
人材定着率の向上
従業員の健康を重視する職場は働きやすく、離職率の低下にもつながります。実際、健康経営優良法人認定企業の離職率は全国平均のおよそ半分程度です(2025年度では認定企業6.1%、全国平均12.1%)。人材の定着によって生産性の向上も期待できます。
金融機関からの評価
認定企業は金融機関・自治体からも高く評価され、融資条件の優遇や補助金の加点、公共事業の入札時にも有利になる制度が拡大しています。事業運営の幅が広がる点も大きなメリットです。
2026年度からの変更点

健康経営優良法人の制度は、2026年度から多くの点で変更されます。認定取得を目指す企業の担当者にとって、変更点を正しく把握しておくことは重要です。では、具体的にどの部分がどのように変わるのか確認していきましょう。
申請単位に関する変更点
健康経営優良法人は、企業だけでなく地方自治体も対象でしたが、従来は首長部局に限り申請可能でした。しかし、教育委員会や公安委員会などの各種委員会は地方自治体内部に存在しながらも一定の独立性を有し、首長が直接指揮命令権を行使できません。
この実態を踏まえ、2026年度からは首長部局と指揮命令系統が異なる委員会単位での申請も認められるようになりました。これにより、自治体の積極的な参加を促し、モデルケースを生み出す狙いがあります。
認定要件の項目に関する変更点
認定要件の具体的な項目に、いくつか重要な変更が加えられています。
ステークホルダーに関する設問
大規模法人部門では、ステークホルダーに関する新たな設問が追加されました。国外グループ企業への対応や、取引先への支援などに関する内容です。より幅広く健康経営を推進する姿勢が求められます。
メンタルヘルスに関する項目
従来は「メンタルヘルス不調への対応」という名称でしたが、2026年度からは「心の健康保持・増進に関する取り組み」と改められます。これに伴い、設問や選択肢も一部見直され、より積極的・包括的な対応が必要とされます。
年差・年代を踏まえた職場づくりの項目
「健康経営の実践に向けた土台づくり」の一部が再編され、「年差・年代を踏まえた職場づくり」という新たな項目が設けられました。女性や高齢従業員への対応策が盛り込まれています。
保険者との連携に関する必須要件
これまで健診データの提供対象は40歳以上の従業員に限られていましたが、2026年度からは大規模法人部門に限り40歳未満の従業員についても提供が必須になります。
育児・介護と仕事との両立の項目
中小規模法人部門では、育児・介護休業法に基づき「育児・介護と仕事の両立」という項目が新設されました。昨年度はアンケート項目として設けられていた内容が、本格的に要件化された形です。
認定要件に関する変更点
認定要件とは、認定を受けるために満たすべき項目を指します。従来は大規模法人部門で16項目中13項目、中小規模法人部門で15項目中8項目が条件でした。
2026年度からは、大規模法人部門で「高齢従業員の健康や体力状況に応じた取り組み」が新たに加わり、17項目中14項目が必須に変更されます。中小規模法人部門でも「育児または介護と就業の両立支援に向けた取り組み」「高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取り組み」の2項目が新たに追加され、全体で17項目中8項目が条件となります。
個別設問に関する主な変更点
2026年度からは個別設問にも複数の見直しが加わっています。
健康経営ガイドブックに基づき追加された項目
大規模法人部門では、健康経営目標やKGI・KPIに関する設問が変更され、ガイドブック改訂内容が反映されました。さらに、健康経営が組織全体に与える影響を検証する設問も新設されています。中小規模法人部門においても、ブライト500関連設問に同様の内容が追加されています。
経営トップによる発信内容
経営トップが発信している内容を具体的に把握できるよう、設問の選択肢が修正されました。大規模法人部門のホワイト500と、中小規模法人部門のブライト500で共通の改訂です。
経営レベルの会議における決定・報告事項
大規模法人部門においては、取締役会で検討された健康経営に関する決定事項や報告事項を確認する設問が追加されました。
PHRデータに関する設問
PHR(Personal Health Record:個人の健康記録)を健康経営にどのように活用しているかを問う内容に変更されました。PHRは施策立案に有効なデータであることから追加された設問です。
仕事と介護・治療の両立支援に関する項目
介護については、2024年5月改正の育児・介護休業法に沿って修正されました。介護休業や介護休暇の利用状況を把握する設問が含まれています。治療についても、厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に基づいて修正されました。
プレコンセプションケアに関する項目
プレコンセプションケア(妊娠前の健康管理)についても改訂が行われました。大規模法人部門は取り組みの有無や具体的な実施内容を確認しますが、中小規模法人部門では実施有無は問われず、認知度調査のみが行われます。
個人事業者に対する支援
契約関係にある個人事業者に対する支援状況を確認するアンケートが新設されました。これは多様な働き方に対応するためのものであり、従業員だけではなく、契約関係にある個人事業者の健康支援の重要性も強調されています。
健康経営優良法人の認定を取得するフロー
2026年度の健康経営優良法人の申請は、すでに8月18日から受付が始まっています。受付終了日は、大規模法人部門が10月10日、中小規模法人部門が10月17日です。余裕を持って準備を整え、期限内に申請を済ませておきましょう。
大規模法人部門では、申請時に経済産業省が実施する「従業員の健康に関する取り組みに関する調査」に回答することが求められます。その回答を経て、認定審査へと進む仕組みです。
一方、中小規模法人部門では、申請の前に保険者が実施する健康宣言事業に参加することが必要です。その後、申請書を作成して日本健康会議認定事務局に提出し、審査を受ける流れとなります。
健康経営優良法人の認定取得のためのポイント
健康経営優良法人の認定を取得するためには、多くの項目への対応が求められます。何に注力すべきか迷う担当者も少なくありません。ここでは、認定取得に向けてとくに押さえておきたいポイントを解説します。
健康経営宣言の実施
大規模法人部門では、経営トップによる健康経営宣言が必須となっています。従業員の健康増進や病気予防を経営課題と位置付け、組織として取り組む姿勢を内外に明確に発信する必要があります。
中小規模法人部門では、保険者の健康企業宣言事業への参加が求められます。健康づくりに関する取り組みやその宣言内容は保険者ごとに異なりますが、職場や従業員の健康を積極的に推進する姿勢が必要です。
健康診断とストレスチェックの確実な実施
両部門ともに健康診断の受診率100%が認定要件です。受診漏れが1人でもある場合、認定は受けられません。未受診者が出ないよう、受診勧奨などの働きかけを行うことが重要となります。
ストレスチェックについては、現在、従業員が50人以上の事業所で義務付けられていますが、2028年施行の法改正後は50人未満の事業所でも必須となります。
生活習慣病予防の対策を実施
評価項目の一つとして、心身の健康づくりに向けた具体的な対策が挙げられます。とくに生活習慣病予防への取り組みは重要です。デスクワーク中心の職場では運動不足になりやすいため、運動の機会を設ける施策(たとえばスポーツイベントの開催など)が効果的です。
さらに、多忙な業務で食生活が乱れがちな場合は、社員食堂での朝食・夕食提供など、栄養バランスに配慮した食事対策も求められます。
まとめ
2026年度の健康経営優良法人制度は、昨年までと比べて多くの変更点があります。とくに、経営トップによる発信内容の明確化や、年差・年代に配慮した職場づくり、個人事業者への支援の充実などが重要なポイントです。また、健康診断やストレスチェックについても、未受診者が出ないよう万全な管理体制を整えておく必要があります。
一方、自社内で十分な対策や運用が難しいと感じる場合は、外部サービスの活用も有効です。ウィーメックスでは、企業の健康診断やストレスチェックなど従業員の健康管理を支援するソリューションを提供しています。社内体制に不安がある場合は、ぜひこの機会に導入を検討してみてください。
出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250310005/20250310005.html)
経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/250424_kenkoukeieigaiyou.pdf)
メディコム 人気の記事
イベント・セミナーEVENT&SEMINAR
お役立ち資料ダウンロード
-

健康経営 人事・総務
【最新法令対応】健康診断実施業務ガイドブック2025年改正に基づく電子申請義務化対応を解説
-
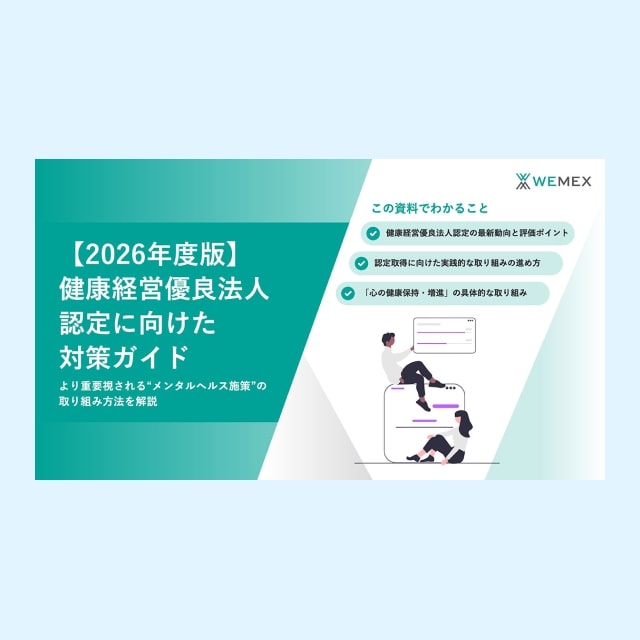
健康経営 人事・総務
【2026年度版】健康経営優良法人認定に向けた対策ガイド
-
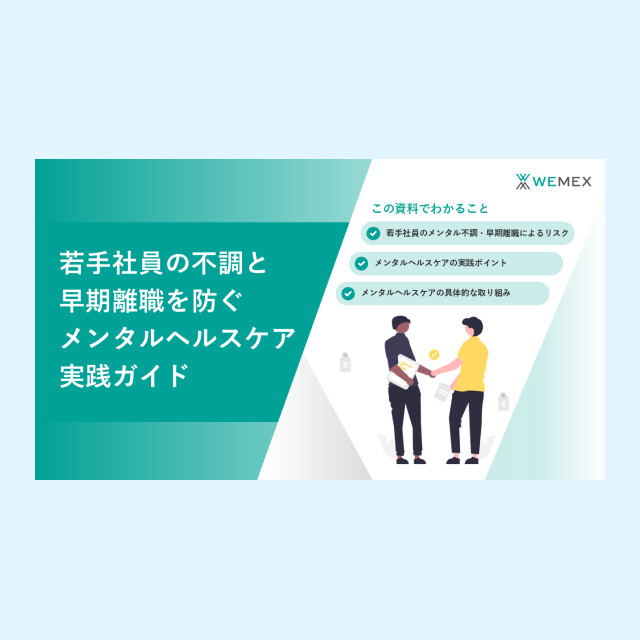
健康経営 人事・総務
若手社員の不調と早期離職を防ぐメンタルヘルスケア実践ガイド
-
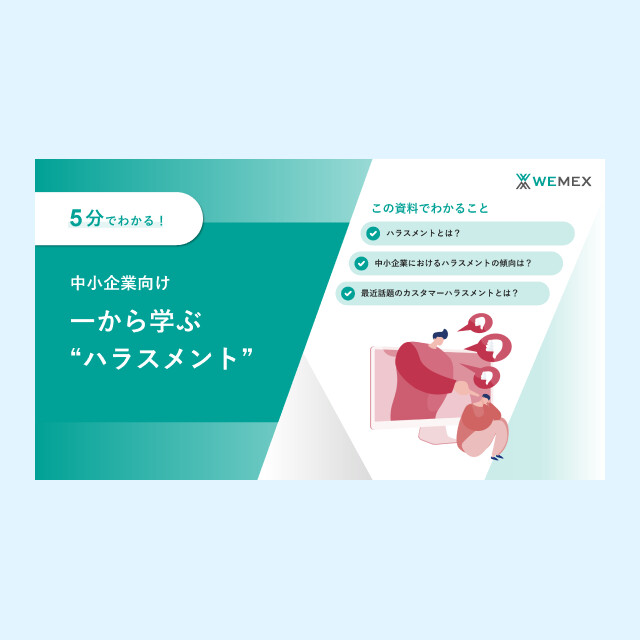
健康経営 人事・総務
中小企業向け 一から学ぶ“ハラスメント”
-
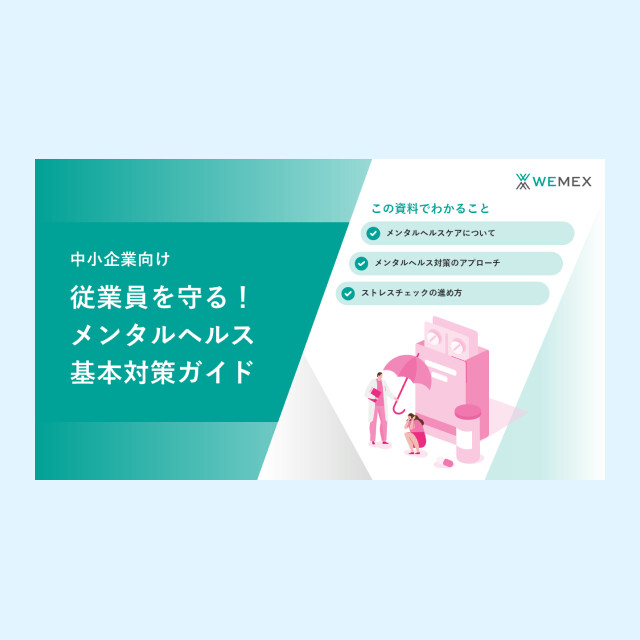
健康経営 人事・総務
中小企業向け 従業員を守る!メンタルヘルス基本対策ガイド
-

健康経営 人事・総務
従業員のメンタル不調~要因と対策~
-

健康経営 人事・総務
法令遵守【チェックリスト付き】健康診断について知るべきこと
-
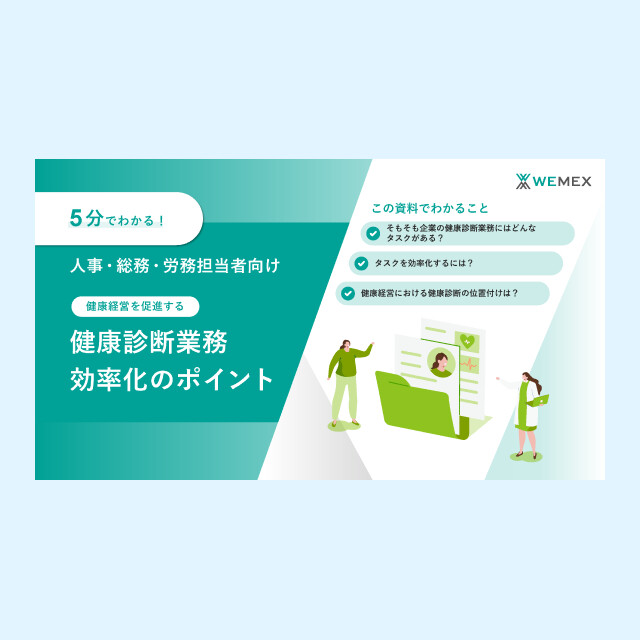
健康経営 人事・総務
健康経営を促進する健康診断業務効率化のポイント