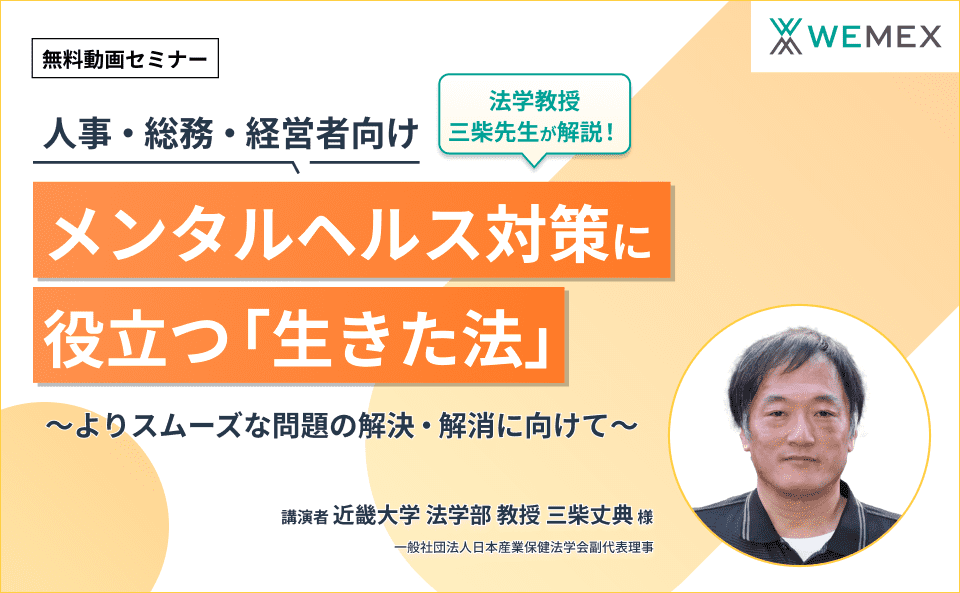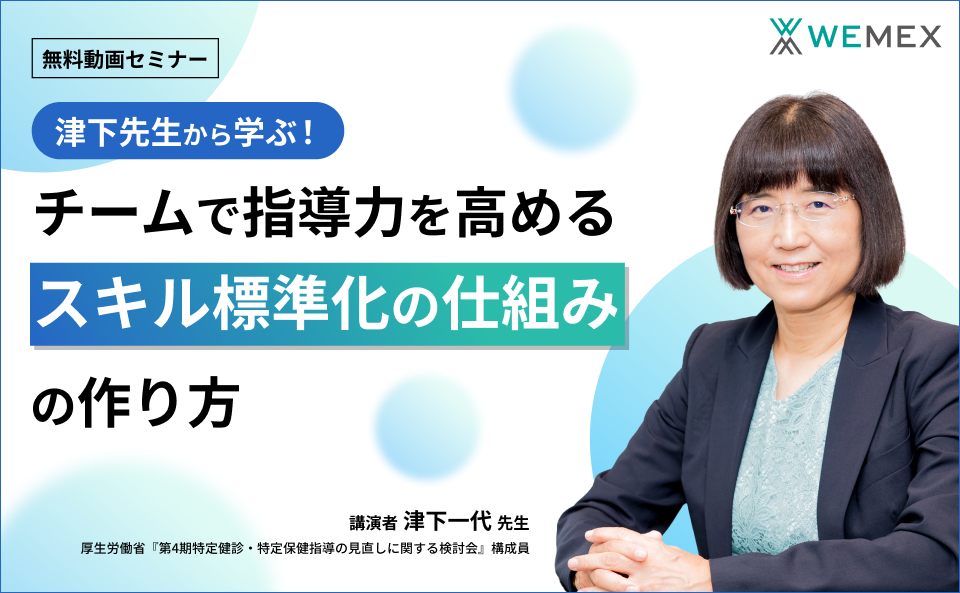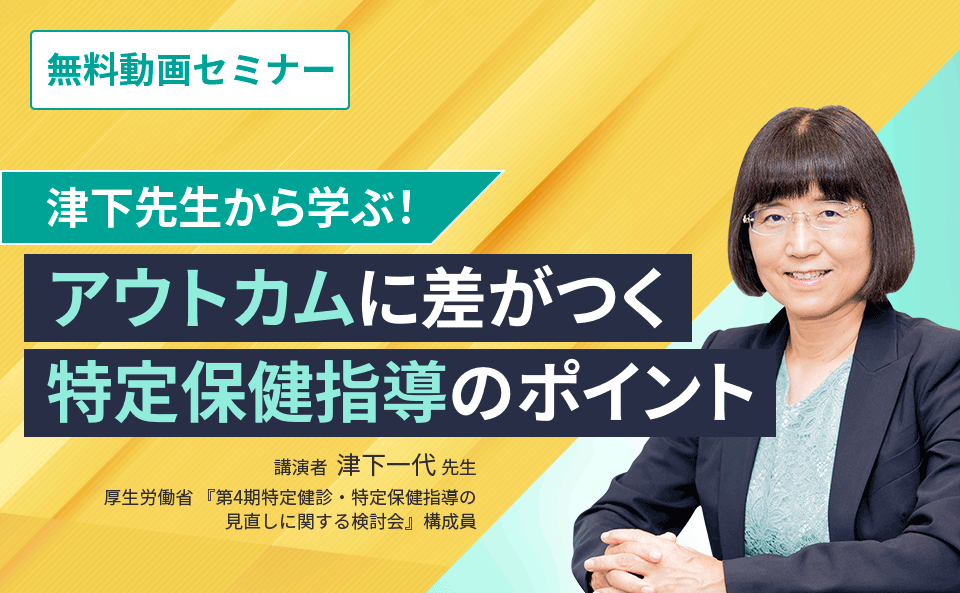目次
健康診断のアウトソーシングとは
健康診断のアウトソーシングとは、健診の準備から実施、事後対応までの一連の業務を外部の専門企業に委託することです。 日程調整や書類のやり取りといった煩雑な事務作業をまとめて任せられるため、人事担当者の業務負担を大幅に軽減できる点が大きなメリットです。
企業には、全従業員を対象とする「定期健康診断」を毎年実施する義務があります。さらに、有害な化学物質や粉じん、騒音など、法令で定められた特定の有害業務に従事する従業員については「特殊健康診断」の実施が義務付けられています。

しかし実際には、対象者のリストアップ、健診機関の選定や予約、従業員への案内、結果の回収・管理など、多くの工数や専門知識を伴います。これらの業務をアウトソーシングすれば、受診率の向上や法令遵守の徹底が可能となり、結果に基づいた事後フォローまで円滑に対応できるようになります。
とくに、人事部門のリソースが限られている企業や、拠点が複数に分かれている企業にとって、有効な選択肢となるでしょう。
関連記事:健康診断は会社の義務!目的や内容・罰則について解説
アウトソーシングできる健康診断の種類
法令で定められている主な健康診断は以下の通りです。
| 種類 | 対象者 | 実施時期 |
|---|---|---|
| 雇入れ時の健康診断 | 新たに常時使用する従業員 | 雇入れの際 |
| 定期健康診断 | 常時使用する全従業員 | 1年以内ごとに1回 |
| 特定業務従事者の健康診断 | 深夜業など特定の業務に従事する従業員 | 配置替えの際および6か月以内ごとに1回 |
| 海外派遣労働者の健康診断 | 6か月以上海外に派遣される従業員 | 派遣の際および帰国後 |
| 給食従業員の検便 | 事業場の食堂などで給食業務に従事する従業員 | 雇入れまたは配置替えの際 |
アウトソーシングサービスの主な対象は、全従業員が受診する「定期健康診断」です。
健康診断の代行会社を利用するメリット
健康診断をアウトソーシングするメリットは、単に業務負担を軽減できるだけではありません。法令遵守や健診体制の強化といった効果も期待できます。ここでは主なメリットを見ていきましょう。
事務負担の大幅な軽減
健康診断を実施する際には、多くの煩雑な事務作業が発生します。アウトソーシングを利用すれば、次のような業務をまとめて委託でき、大幅な負担削減につながります。
| 業務内容 | 詳細説明 |
|---|---|
| 医療機関の選定・予約 | 全国の提携機関から最適な施設を選び、従業員の予約調整まで対応 |
| 従業員への案内・連絡 | 受診対象者抽出、健診案内送付、予約リマインド、受診勧奨などを代行 |
| 費用の精算業務 | 複数医療機関からの請求書を取りまとめ、一括で精算処理 |
| 結果のデータ化 | 健診結果を回収後、データ化して納品 |
健康診断に要する事務作業の多くを手放し、担当者は本来の業務により集中できるようになります。
法令遵守とリスク管理の強化
健康診断は労働安全衛生法によって実施が義務付けられており、違反した場合には罰則も科されます。さらに、労働基準監督署への報告や異常所見者への対応など、健診後に講じるべき措置も法律で定められています。そのため、法令の理解が不十分だと、意図せず違反にあたる恐れもあります。
こうしたリスクを避けるためには、業務に精通した代行サービスを活用することが効果的です。代行サービスのサポートを受けることで、義務履行の抜け漏れや遅延を防ぎ、確実な法令遵守につなげることができます。加えて、健診結果は機微性の高い個人情報であるため、セキュリティ体制の整った代行会社を選定すれば、情報漏洩リスクを低減し、安全性の高いリスク管理を実現できます。
効率的な健診体制の構築
健康診断のアウトソーシングは、健診体制の効率化にも大きな効果を発揮します。従業員数や拠点数が増えると、健診の実施や結果管理の負担が膨らみ、全社で統一した体制を整えることが難しくなります。
全国に医療機関とのネットワークを持つ代行会社を利用すれば、各拠点から近い受診機関を選べるため、従業員の利便性が高まり、受診率の向上も期待できます。また、受診状況や健診結果をオンラインで一元管理できるため、企業側の業務効率も格段に向上します。
その結果、人事担当者は拠点ごとに病院を探したり、各拠点から送付される健診結果を個別に取りまとめたりする必要がなくなり、効率的かつスムーズに健診体制を構築できるようになります。
【企業向け】健康診断の実施方法・流れ

健康診断の準備や運営を円滑に進めるには、実施方法や流れを正しく理解しておくことが大切です。ここでは、健康診断を対象とした基本的な流れを紹介します。
- 対象者の確認
- 実施時期の調整
- 健診機関の選定
- 社内周知
- 健診実施と事後措置
各ステップの具体的な内容と注意点を解説します。
1.対象者の確認
まずは、健康診断の受診対象者を漏れなく正確に把握することが重要です。定期健康診断は「常時使用するすべての従業員」が対象となります。パートやアルバイトであっても、次の条件に該当する場合は受診が義務付けられています。
【健康診断の実施が義務となる条件】
- 雇用期間の定めがない、または1年以上の雇用が見込まれる場合
- 週の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上である場合(おおむね2分の1以上であれば実施が望ましい)
対象者を正しく抽出するためには、各従業員の雇用契約や労働時間を確認し、管理台帳などに基づいてリストアップしておくと確実です。
2.実施時期の調整
健康診断は法令で実施時期が定められているため、計画的なスケジュール調整が欠かせません。それぞれの健康診断の種類ごとに、適切なタイミングを把握しておくことが重要です。
- 雇入れ時の健康診断は、従業員を雇い入れる際に実施します。
- 定期健康診断は、1年以内ごとに1回の頻度で全従業員に対して行う必要があります。
- 特定業務従事者の健康診断は、配置換えの際と6か月以内ごとに1回実施します。
法律で定められた時期を守れば、自社の都合に合わせて実施時期を柔軟に設定することが可能です。再検査(二次健診)なども考慮し、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
3.健診機関・医療機関の選定
実施時期が決まったら、健診機関や医療機関を選定します。選定の際には、以下のポイントが重要です。
- 対応能力:対象人数や希望時期に一度に対応できるキャパシティがあるか
- 場所:従業員が受診しやすい場所にあるか、もしくは健診車による社内での集団健診が可能か
- 検査項目:労働安全衛生法および規則で定められた必須項目をすべて満たしているか
費用相場は、健康診断で1人あたり5,000円〜15,000円程度です。健康診断の費用は法律で企業が負担することになっており、がん検診や脳ドックなどオプション検査は従業員の自己負担でも問題ありません。
4.健康診断内容の社内周知
健診機関と日程が確定したら、対象となる従業員へ健康診断の内容を周知します。周知の際は、従業員にとって健康診断の受診は法令上の義務であることをはっきりと伝えましょう。加えて、健診日時や場所、所要時間、必要な持ち物なども具体的に案内します。
とくに受診前の飲食制限(例:10時間以上の絶食)や当日の服装(着脱しやすい服装など)、受診や健診結果に影響が大きい事項については、詳しく説明しておくことが重要です。さらに、よくある質問をまとめた資料を用意し事前配布すれば、個別の問い合わせを減らし運営の効率化につながります。
5.健診実施と事後措置
健康診断は実施するだけでなく、診断後の事後措置までが企業の責務となります。
まず従業員全員に受診結果を通知します。「異常の所見あり」とされた従業員に対しては、速やかに再検査や精密検査の受診を勧奨し、必要に応じて健康状態を確認します。
さらに企業には、3か月以内に産業医への意見聴取を行う義務があります。その内容を踏まえて、「通常勤務可能」「就業制限」「要休業」などの区分を判断し、労働時間の短縮や業務内容の変更など必要な配慮措置を講じます。
健康診断実施のよくある課題
企業における健康診断の実施には多くの課題が潜んでいます。事前にこれらの課題を把握しておくことで、効率的な準備や法令違反のリスク回避につながります。ここでは、とくに多い3つの課題について解説します。
スケジュール調整の手間
健康診断の実施にあたっては、従業員と医療機関、双方の都合をすり合わせたスケジュール調整が必要です。この調整作業には多くの時間がかかります。
社内スケジュールの調整では、24時間稼働の工場や繁忙期のある部署などでは業務への影響を考慮した日程設定が求められます。健康管理の重要性を日頃から伝え、現場の事情を丁寧にヒアリングしながら計画を立てることが重要です。
また、医療機関との日程調整も欠かせません。自社の希望日と医療機関の予約可能日をすり合わせて予定を決める必要があり、人気の医療機関は早期に予約枠が埋まることも少なくありません。健診車を職場に呼ぶ場合には、当日の待機場所や従業員の動線確保、案内のための打ち合わせなどの事前調整も必要になります。
未受診者・異常所見者への受診勧奨の負担
健康診断の実施後も、体調不良などで受診できなかった従業員や受診を拒否する従業員に対して、改めて受診を促す必要があります。とくに受診への意欲が低い従業員への個別フォローは、人事担当者にとって精神的な負担も大きくなりがちです。
異常所見が見つかった場合の二次健診(精密検査等)の受診勧奨はさらに難航しやすいものです。二次健診の受診は努力義務であり、企業に強制権限はありませんが、対応を怠ると安全配慮義務違反を問われる可能性もあります。
従業員には二次健診の重要性を丁寧に説明し、粘り強く受診を促すことが求められます。未受診者リストの作成や繰り返し個別通知・フォローアップの徹底など、まずは丁寧な対応が重要です。どうしても受診率向上が難しい場合には、専門機関へのアウトソーシングも検討すると、担当者の負担軽減と適切な対応の両立が図れます。
関連記事:受診勧奨とは?重要性や実施基準やポイントを紹介
法律に基づく対応の煩雑さ
健康診断実施後も、労働安全衛生法などの法令に基づきさまざまな対応が求められます。主な義務には以下のようなものがあります。
| 法律に基づく対応 | 詳細説明 |
|---|---|
| 健康診断個人票の作成・保管 | 健康診断結果を記録し、原則5年間(特殊健診の一部は30年間)保存する義務がある |
| 労働基準監督署への結果報告 | 常時50人以上の従業員がいる事業所では「定期健康診断結果報告書」の提出が義務付けられている |
| 医師からの意見聴取 | 異常所見が確認された従業員については、3か月以内に医師等の意見を聴取する |
| 就業上の措置の決定・実施 | 医師の意見に基づき、必要があれば労働時間の短縮や作業転換などの配慮措置を実行する |
特殊健診を要する職場では、健診内容や記録の保存期間・報告義務も異なるため、さらに対応が煩雑になります。事務作業の漏れや誤りは法令違反となり、企業リスクを高める原因となるため、適宜アウトソーシング等も活用してリスクを最小限に抑える取り組みが推奨されます。
健康診断代行サービスの選び方
健康診断代行サービスは、自社に合ったものを選ぶことが重要です。代行サービスにはそれぞれ特徴があり、主に次のタイプに分けられます。
| 代行サービスのタイプ | 特徴 |
|---|---|
| 総合サポートタイプ | 健康診断に関わる業務全般を包括的に支援する |
| 医療領域サポートタイプ | ストレスチェックなどのメンタルヘルス領域にも対応できる |
| 福利厚生充実タイプ | 従業員の健康意識を高めるプラスアルファの機能が充実している |
| バックオフィス連携タイプ | 他の総務人事関連業務とあわせて委託できる |
代行サービスを選ぶ際は、まず自社の課題を明確にしましょう。事務作業の負担軽減を重視する場合と、法令遵守の不安を解消したい場合では適したサービスが異なります。
課題を明確化したうえで、委託できる業務内容や全国の提携医療機関数、健診結果のデータ化方法などを確認し、実際のニーズに合うかを判断します。最後に料金プランとセキュリティ体制を比較検討すると、より的確な代行サービスを選定しやすくなります。
まとめ
健康診断業務は人事担当者にとって大きな負担となりがちです。健康診断代行サービスを上手に活用すれば、業務負担を大幅に軽減することができます。
ウィーメックスの健診代行サービスを利用することで、健康診断に関する業務負担を大幅に削減できます。健診機関との契約交渉や予約手配、受診案内や変更対応、進捗管理や請求・精算業務までをワンストップで委託でき、事務作業を約90%減らすことが可能です。
まずは以下よりお気軽にご相談ください。
メディコム 人気の記事
イベント・セミナーEVENT&SEMINAR
お役立ち資料ダウンロード
-

健康経営 人事・総務
【最新法令対応】健康診断実施業務ガイドブック2025年改正に基づく電子申請義務化対応を解説
-
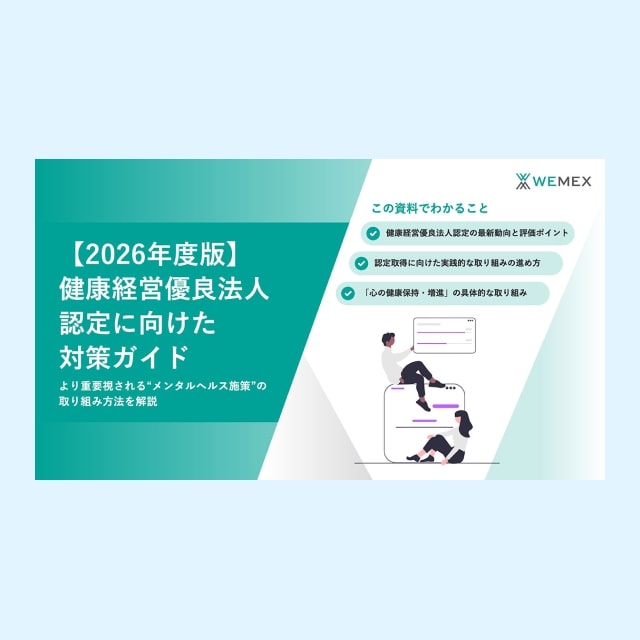
健康経営 人事・総務
【2026年度版】健康経営優良法人認定に向けた対策ガイド
-
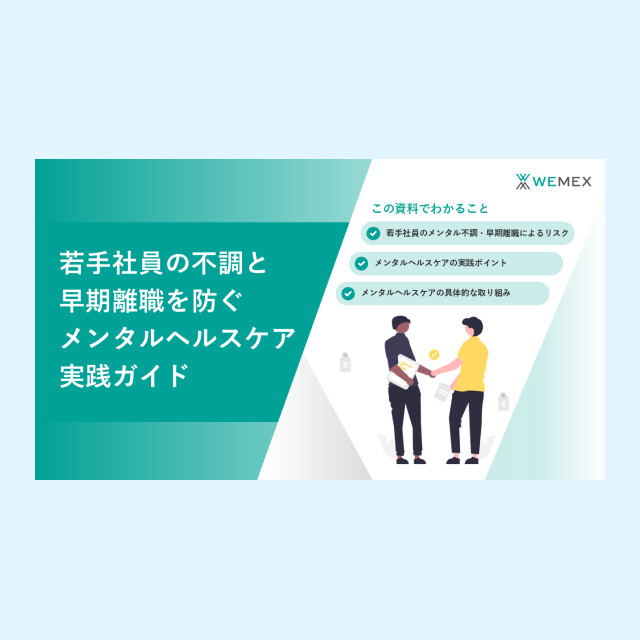
健康経営 人事・総務
若手社員の不調と早期離職を防ぐメンタルヘルスケア実践ガイド
-
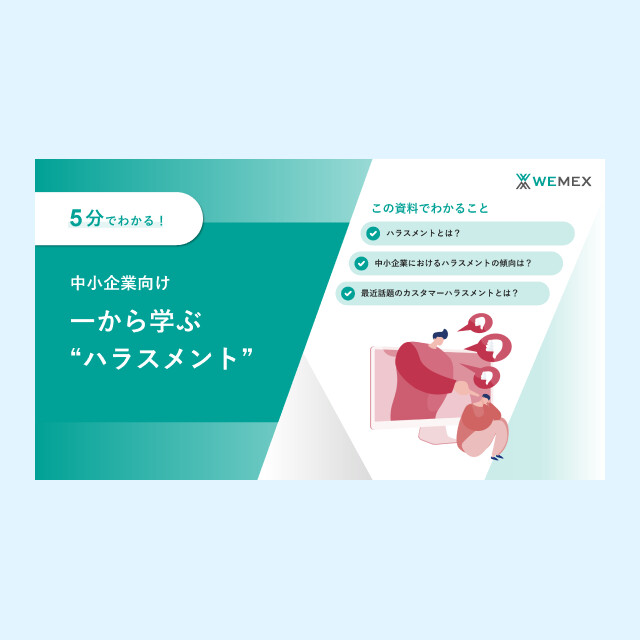
健康経営 人事・総務
中小企業向け 一から学ぶ“ハラスメント”
-
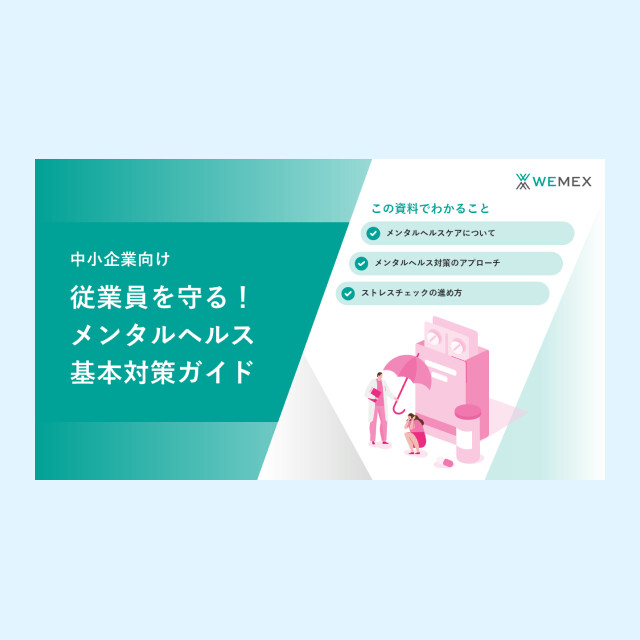
健康経営 人事・総務
中小企業向け 従業員を守る!メンタルヘルス基本対策ガイド
-

健康経営 人事・総務
従業員のメンタル不調~要因と対策~
-

健康経営 人事・総務
法令遵守【チェックリスト付き】健康診断について知るべきこと
-
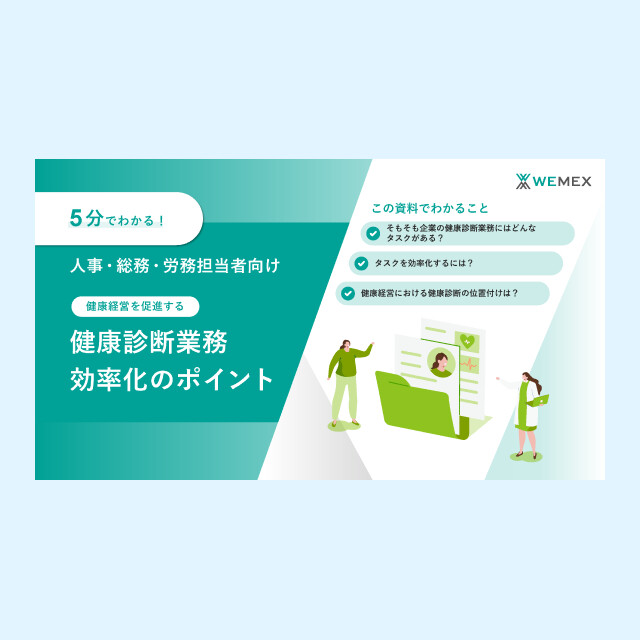
健康経営 人事・総務
健康経営を促進する健康診断業務効率化のポイント