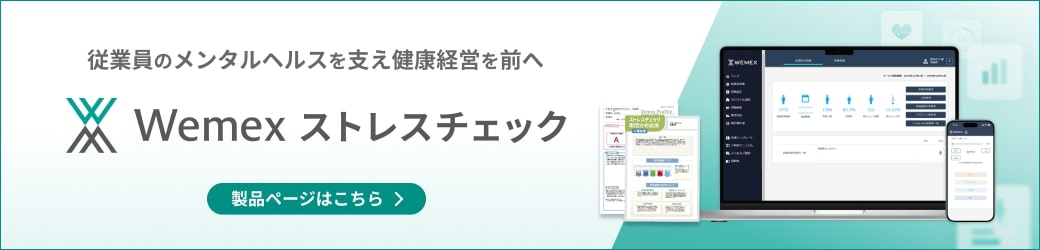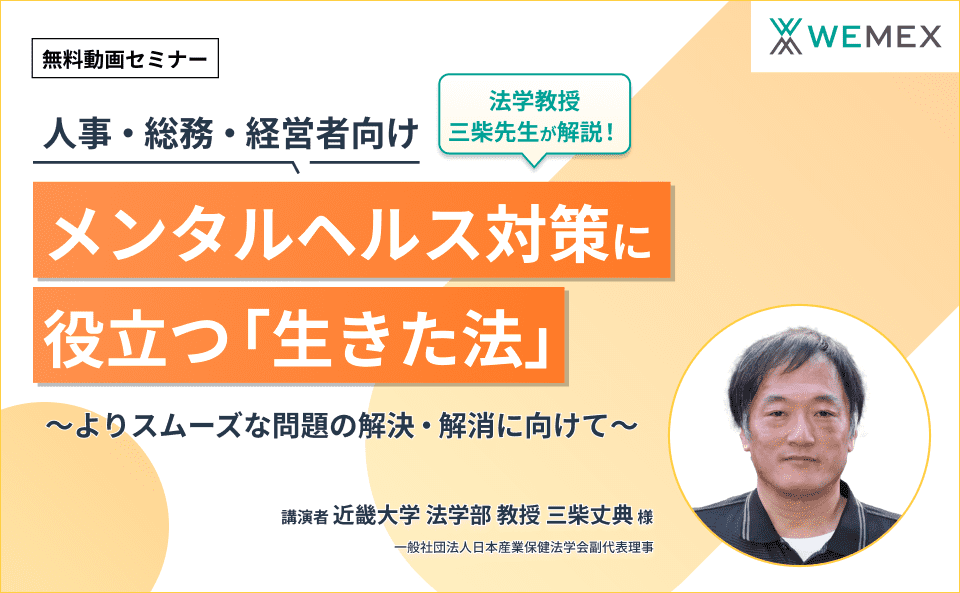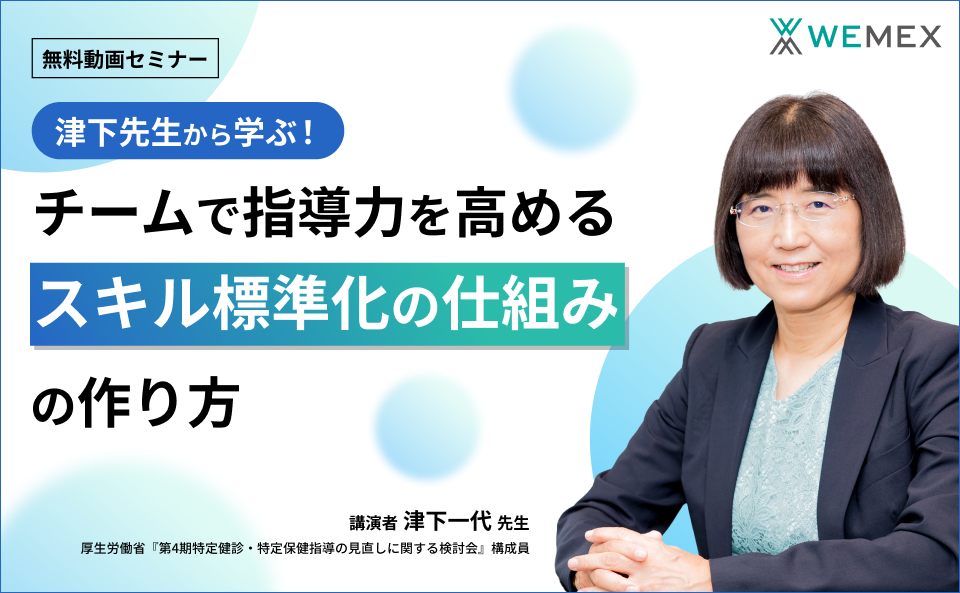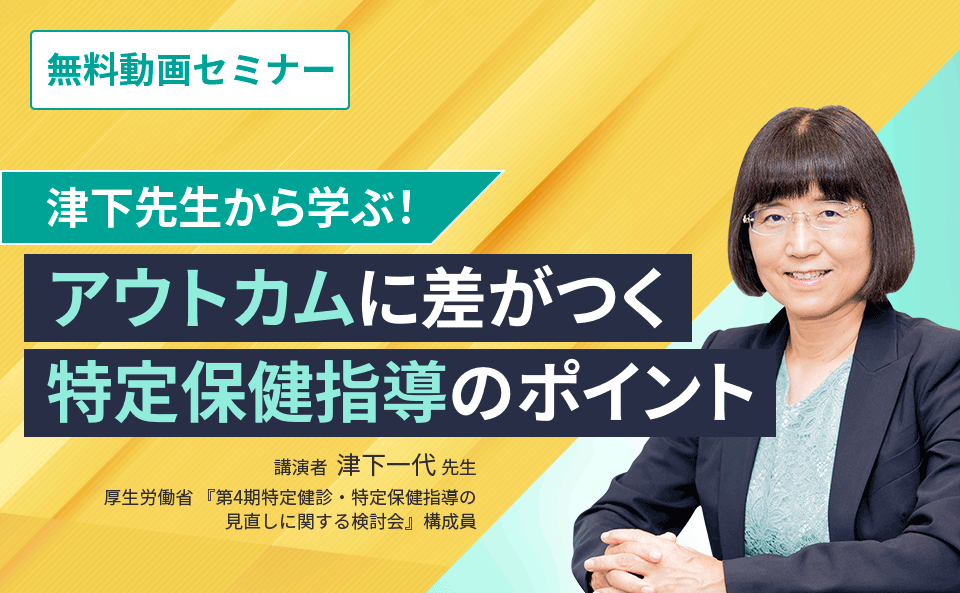ストレスチェックで離職を防ぐ!リスクを早期発見する方法と予防策
毎年ストレスチェックを実施していても、結果の活用方法が分からず、形式的になっている職場も少なくないようです。 しかしストレスチェックは、従業員の健康リスクを把握するだけでなく、離職防止にもつながる重要な仕組みです。本記事では、メンタルヘルス不調が離職へと至る背景、ストレスチェックで離職の兆候を見つける方法、そして離職を防ぐための具体的な対策を解説します。 法律上の義務として終わらせるのではなく、働きやすい職場づくりの手がかりとして積極的に活用していきましょう。
※本内容は公開日時点の情報です
目次
ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、従業員のストレス状態を把握するための検査制度です。実施することで、個人の心理的な状態だけでなく、職場全体のメンタルヘルスの状況も確認できます。
この制度は、メンタルヘルスケアの取り組みにおける「一次予防」の位置づけにあります。

| 取り組み | 詳細 |
|---|---|
| 一次予防 | 従業員がストレスに気づき、自ら対処できるよう支援するとともに、職場環境を改善して不調を未然に防ぐ |
| 二次予防 | メンタルヘルス不調を早期に発見し、悪化を防ぐために適切な対応を行う |
| 三次予防 | 不調により休職した従業員の職場復帰を支援する |
関連記事:ストレスチェックは会社の義務!対象者や実施の流れを解説
ストレスチェックの目的
ストレスチェックの目的は、単なる情報収集ではありません。従業員自身が自分のストレス状態を把握し、メンタルヘルス不調を防ぐことが最大の狙いです。
これにより、従業員の心身の健康が守られるだけでなく、エンゲージメントや生産性の向上、さらには離職率の低下といった効果も期待できます。企業にとっても従業員にとっても、大きな意義を持つ制度といえるでしょう。
法的な義務付けと対象者
ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づき2015年12月から制度化されました。常時50人以上の従業員を使用する事業場では、年1回の実施が法律で義務付けられています。
一方、常時50人未満の事業場については現在「努力義務」にとどまっています。しかし、今後は義務化されることが決まっているため、早めの体制整備が求められます。
対象者は正社員だけでなく、条件を満たすパートタイム従業員も含まれます。
【ストレスチェックの対象者の要件】
- 契約期間が1年以上、または1年以上となる見込みであること
- 週の労働時間が、同じ事業場の正社員の4分の3以上であること(2分の1以上の場合も実施が望ましい)
離職につながるメンタルヘルス不調
メンタルヘルス不調による離職は、いまや社会的な課題となっています。厚生労働省が実施した「令和5年 労働安全衛生調査」によれば、過去1年間にメンタルヘルス不調を理由に退職した従業員がいた事業所の割合は6.4%でした。前年の5.9%から上昇しており、問題が深刻化していることが分かります。
このような離職が発生すると、新たな人材の採用・教育にコストがかかるだけでなく、残された従業員に業務負担が集中し、さらなる不調者を生む悪循環に陥る恐れがあります。加えて、企業のイメージ低下にもつながりかねません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r05-46-50_kekka-gaiyo01.pdf)
ストレスチェックは離職防止に有効
ストレスチェックは、次の3つの観点から離職防止に効果を発揮します。
退職リスクの早期発見

ストレスチェックの結果から、従業員が退職を考えている可能性を見つけ出せます。
たとえば「仕事の負担感」や「職場の人間関係」「将来への不安」などの項目でストレスが高い従業員の場合、企業に不満がある可能性が高いと考えられます。
集団分析による職場環境の改善
個人結果だけでなく、ストレスチェックを集団分析することで、離職リスクの高い部署や職場環境を特定できます。「業務負荷が過大」「上司や同僚からのサポート不足」といった傾向が見えれば、長時間労働の是正やコミュニケーション促進など、環境改善の施策を検討・実行することが重要です。
サイレント退職への対応
サイレント退職とは、退職の意思を表明せずに静かに準備を進める状態を指します。ストレスチェックを行うことで、モチベーション低下や心身の不調といった兆候を数値や傾向として把握でき、表面化しにくいリスクを早期に見抜くことができます。
さらに、人事データとストレスチェックの結果を組み合わせれば、より精度の高い分析と的確な対応が可能となります。
ストレスチェックで離職リスクを早期発見する方法
ストレスチェックを適切に活用すれば、従業員の離職リスクを早めに把握し、具体的な対策に結びつけることができます。ここでは、その活用方法を4つ紹介します。
従業員自身がストレス状況を把握
ストレスチェック実施後に結果を通知するだけでは不十分です。従業員が自分自身のストレス状況に気づき、セルフケアにつなげられるよう、生活習慣の改善やストレス解消法といった情報を提供しましょう。
また、社内外の相談窓口を案内し、深刻化する前に専門的な支援を受けられる体制を整えることも大切です。企業としては、結果や日常の様子から離職の兆候を早めにキャッチし、適切に対応していく必要があります。
高ストレス者を把握
ストレスチェックの結果から「高ストレス者」と判断される従業員は、心理的な負担が大きい状態にあります。判定基準は衛生委員会などで専門家の意見を踏まえて決定し、厚生労働省が示す評価基準の一例は以下のとおりです。
【高ストレス者の評価基準(職業性ストレス簡易調査票・57項目)】
- 「心身のストレス反応」の合計点数が77点以上
- または以下の両方を満たす場合
- 「仕事のストレス要因」と「周囲のサポート」の合計点数が76点以上
- 「心身のストレス反応」の合計点数が63点以上
しかし、高ストレス者は「会社に知られたくない」「人事評価に影響するのでは」と懸念し、医師による面接指導を希望する割合が低い傾向があります。実際、厚生労働省「令和5年 ストレスチェックの実施状況」によると、面接指導を受けた高ストレス者は全国でわずか0.46%にとどまっています。
集団分析で組織課題を特定
ストレスチェックは個人単位の把握にとどまらず、部署や職種ごとに集団分析を行うことで職場全体の課題を特定できます。業務負担の偏りや人間関係の不調和などを客観的に示し、改善策の立案につなげることができます。これにより、離職リスクが高い職場の早期改善が可能となります。
継続的にモニタリングを実施
ストレスチェックは一度実施して終わりではなく、継続的にモニタリングして改善のサイクルを回すことが重要です。他の取り組みと組み合わせることで、従業員の状況をより多角的に把握できます。
- エンゲージメントサーベイ
ストレスチェックでは測れない「仕事への熱意」「組織への愛着」などを調査し、離職リスクの兆候を把握できます。 - 1on1面談
上司と従業員が定期的に話す機会を設け、業務だけでなくキャリアや私生活の課題も共有できる場をつくることが、信頼関係の構築や早期対応につながります。
複数の方法を組み合わせて従業員の状態を把握することで、より効果的な離職防止策を実行できるようになります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf)
厚生労働省ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/001830073.pdf)
ストレスチェックを活用した離職の予防策
ストレスチェックの結果を確認するだけでは、離職防止にはつながりません。結果を効果的に活用し、具体的な施策につなげることが重要です。ここでは、離職を予防するための5つの取り組みを紹介します。
- セルフケアの強化
- 高ストレス者のフォロー強化
- 職場環境の改善
- ラインケアの強化
- 柔軟な働き方の推進
セルフケアの強化
セルフケアとは、従業員が自らのストレスに気づき、適切に対処する取り組みです。企業としてセルフケアの重要性を発信し、ヘルスリテラシー(健康に関する情報を理解・活用する力)を高めるための研修を実施すると効果的です。
セルフケア研修には、次のような内容を盛り込みましょう。
- ストレスやメンタルヘルスに関する基礎知識
- セルフケアの重要性
- 心の健康問題への向き合い方
- ストレス状態に気づく方法
- 予防と軽減のための工夫
- 具体的なストレス対処法
- 専門家への相談の有用性
- 社内外の相談窓口に関する情報
セルフケア研修は、従業員が自らの健康を守る力を高めるだけでなく、必要に応じて面接指導や相談を申し出る行動を後押しします。その結果、メンタルヘルス不調の早期発見・早期対応にもつながります。
関連記事:セルフケアとは?メンタルヘルスケアの重要性と推進のポイント
メンタルヘルス研修はなぜ必要?実施するメリットや効果を高める方法も解説
高ストレス者のフォロー強化
高ストレス者を放置すると、心身の不調が悪化し、離職リスクが高まります。そのため、複数の手段を組み合わせた丁寧なフォローが欠かせません。以下に有効な対策と期待できる効果をまとめます。
| 対策 | 効果 |
|---|---|
| 医師による面談指導の目的や内容の周知 | 面談を希望する際の心理的ハードルを下げられる |
| 相談窓口の設置 | 安心して相談できる環境を提供できる |
| 全員を対象とした面談 | 高ストレス者にアプローチしやすくなる 職場課題を発見できる |
高ストレス者を見つけるだけでは離職防止にはつながりません。状況を継続的に把握して声かけを行い、必要に応じて労働時間の短縮など具体的な就業上の措置を講じることが重要です。
職場環境の改善
職場環境はストレスの根本要因となりやすく、改善することは離職防止にも直結します。集団分析で明らかになった課題をもとに、現場に即した改善策を実行しましょう。
| 集団分析で見つかる課題 | 離職防止施策 |
|---|---|
| 仕事の量的負担が大きい |
業務配分・人員体制の見直し 業務効率化ツールの導入 |
| 仕事の裁量権が小さい |
権限移譲の推進 従業員の意見を尊重する風土づくり |
| 上司・同僚の支援が少ない |
1on1面談の導入 コミュニケーション活性化施策 |
| ハラスメントのリスクがある |
ハラスメント研修の実施 相談窓口の設置と周知 |
このように、職場環境の改善は従業員の定着率を高めるための有効な手段であり、離職予防の基盤となります。
ラインケアの強化
ラインケアとは、課長や部長といった管理監督者が部下の心身の健康状態に気を配り、相談対応などを行う取り組みです。日常的に部下と接している上司が異変に気づけることで、メンタルヘルス不調の早期発見と離職防止につながります。
管理監督者に対しては、ラインケア研修を実施し、部下との適切な関わり方を学ぶ機会を提供しましょう。マネジメントスキルを高めることで、従業員が安心して相談しやすい関係を築けます。
さらに、上司への相談に加えて社内外に専門の相談窓口を設け、従業員がいつでも相談できる体制を整えることも重要です。
関連記事:ラインケアでは何を行うべき?実施するメリットや注意点も解説
柔軟な働き方の推進
従業員それぞれのライフステージや価値観に合わせ、時間や場所にとらわれずに働ける仕組みを整えることは、ワークライフバランスの向上と離職防止に効果的です。主な制度とその効果は以下のとおりです。
| 制度 | 効果 |
|---|---|
| テレワーク | 通勤による負担の軽減が可能 |
| フレックスタイム制 | 育児や介護など、個人の事情に合わせて働きやすくなる |
| 時間単位年休 | 年次有給休暇を1時間単位で取得できる制度 短時間の私用に対応しやすく、休暇の取得もしやすくなる |
ただし、制度を導入するだけでは不十分です。上司が率先して休暇を取得し、業務の相互フォロー体制を整えるなど、従業員が安心して制度を利用できる風土をつくることが欠かせません。
まとめ
ストレスチェックは離職防止に有効な仕組みですが、運用には多くの手間がかかります。従業員への案内、結果の集団分析、高ストレス者への対応など、人事担当者の負担が大きく、実施後の活用が十分に進まないケースも少なくありません。
こうした課題に対しては、外部サービスの活用も効果的です。ウィーメックスのストレスチェックサービスでは、準備から実施後のフォローまで幅広く代行するだけでなく、受検結果に応じた動画提供や研修の実施など、メンタルヘルス改善や離職防止に直結するサポートをご用意しています。
まずはお気軽にご相談ください。
メディコム 人気の記事
イベント・セミナーEVENT&SEMINAR
お役立ち資料ダウンロード
-

健康経営 人事・総務
【最新法令対応】健康診断実施業務ガイドブック2025年改正に基づく電子申請義務化対応を解説
-
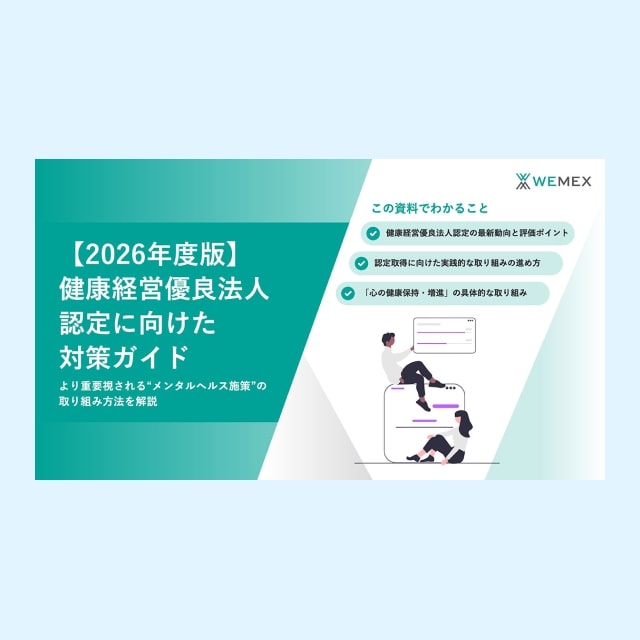
健康経営 人事・総務
【2026年度版】健康経営優良法人認定に向けた対策ガイド
-
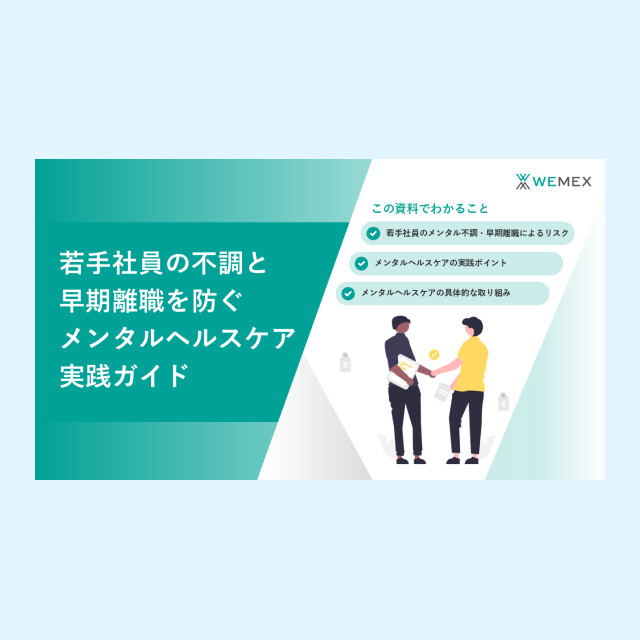
健康経営 人事・総務
若手社員の不調と早期離職を防ぐメンタルヘルスケア実践ガイド
-
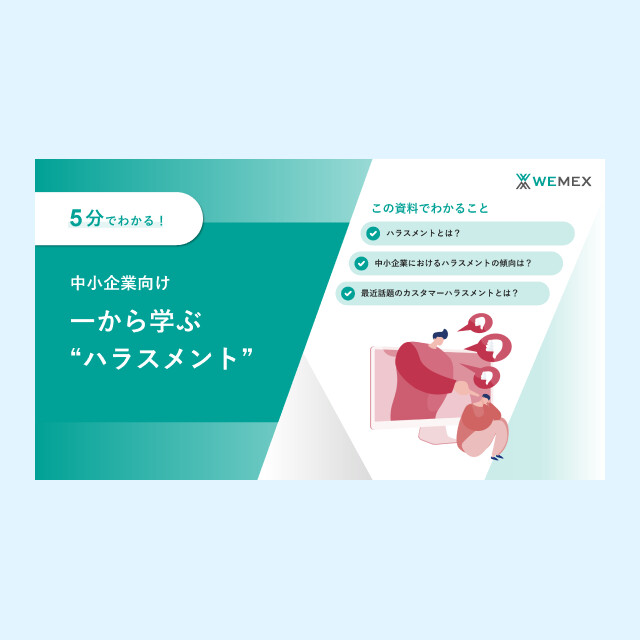
健康経営 人事・総務
中小企業向け 一から学ぶ“ハラスメント”
-
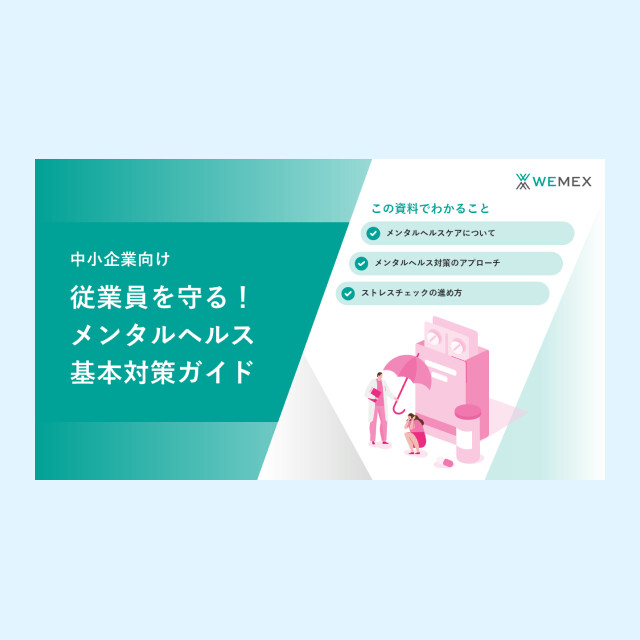
健康経営 人事・総務
中小企業向け 従業員を守る!メンタルヘルス基本対策ガイド
-

健康経営 人事・総務
従業員のメンタル不調~要因と対策~
-

健康経営 人事・総務
法令遵守【チェックリスト付き】健康診断について知るべきこと
-
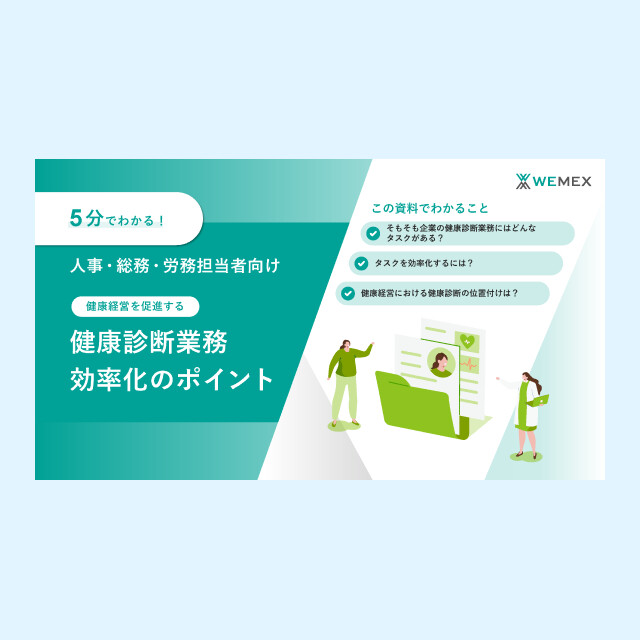
健康経営 人事・総務
健康経営を促進する健康診断業務効率化のポイント