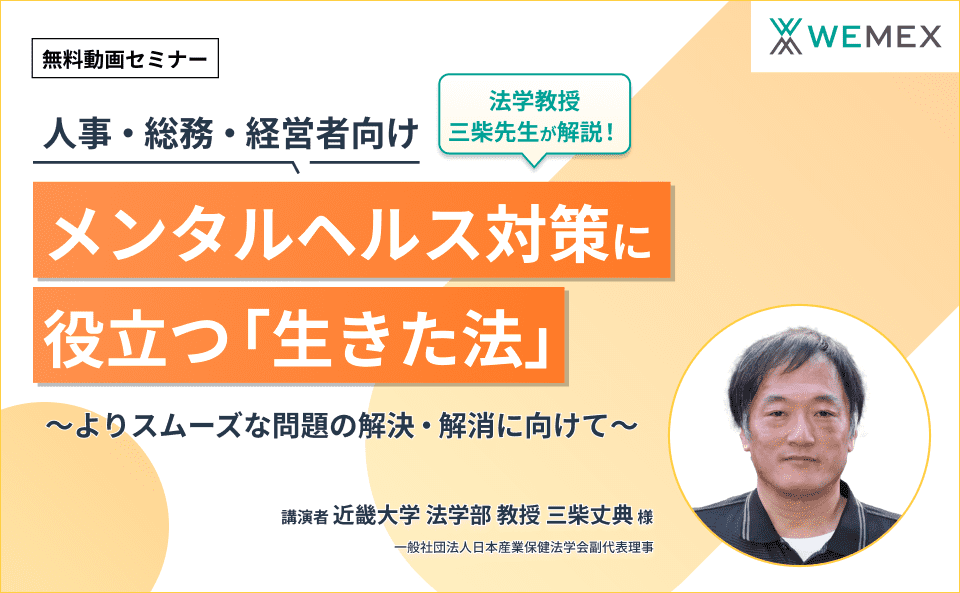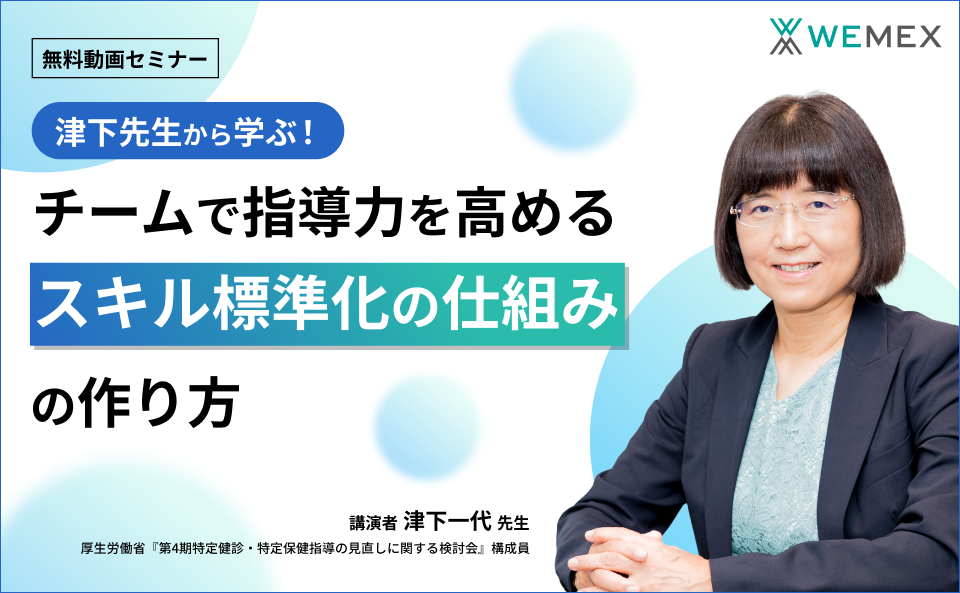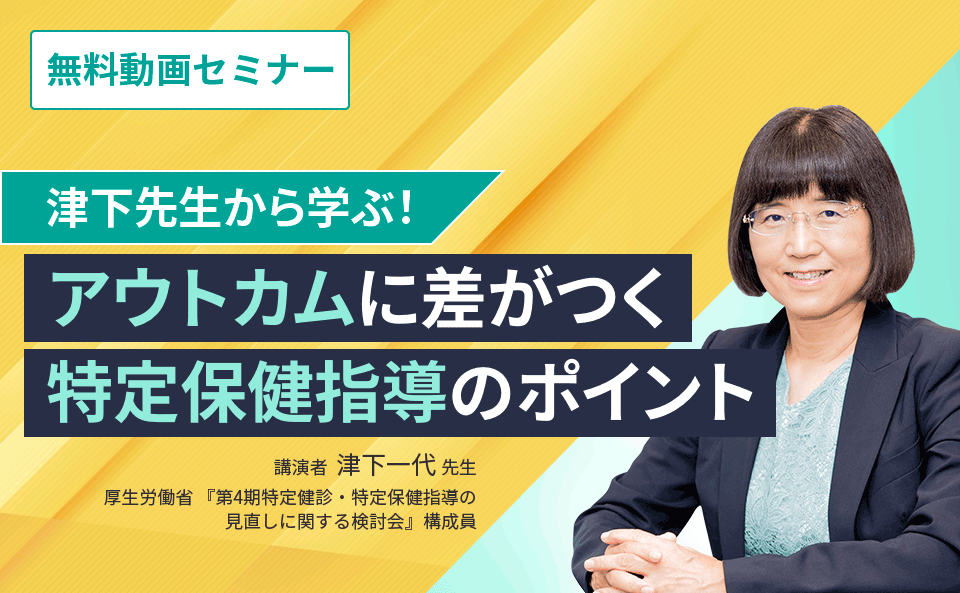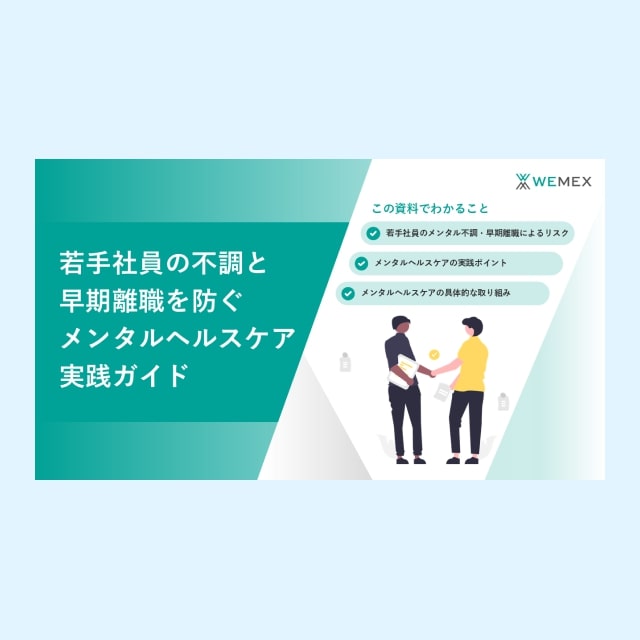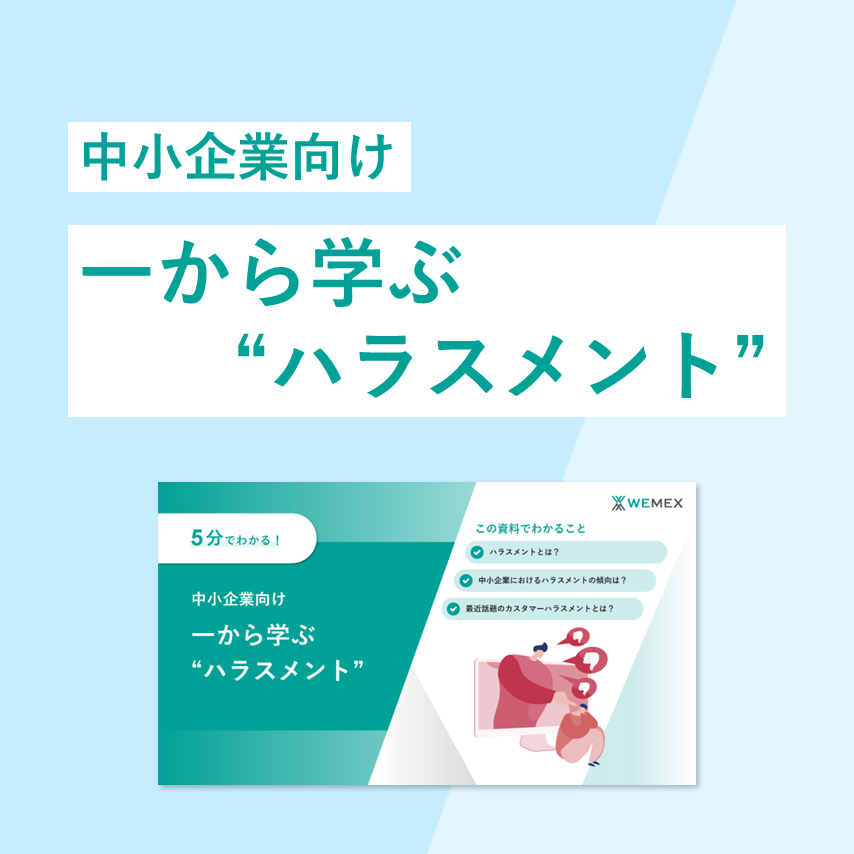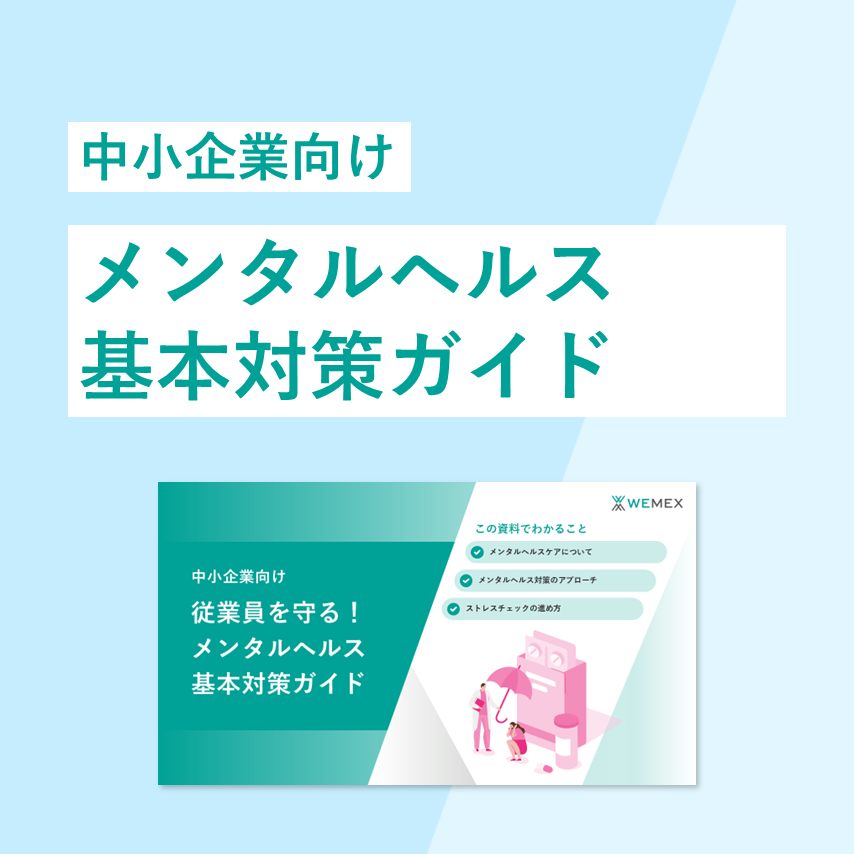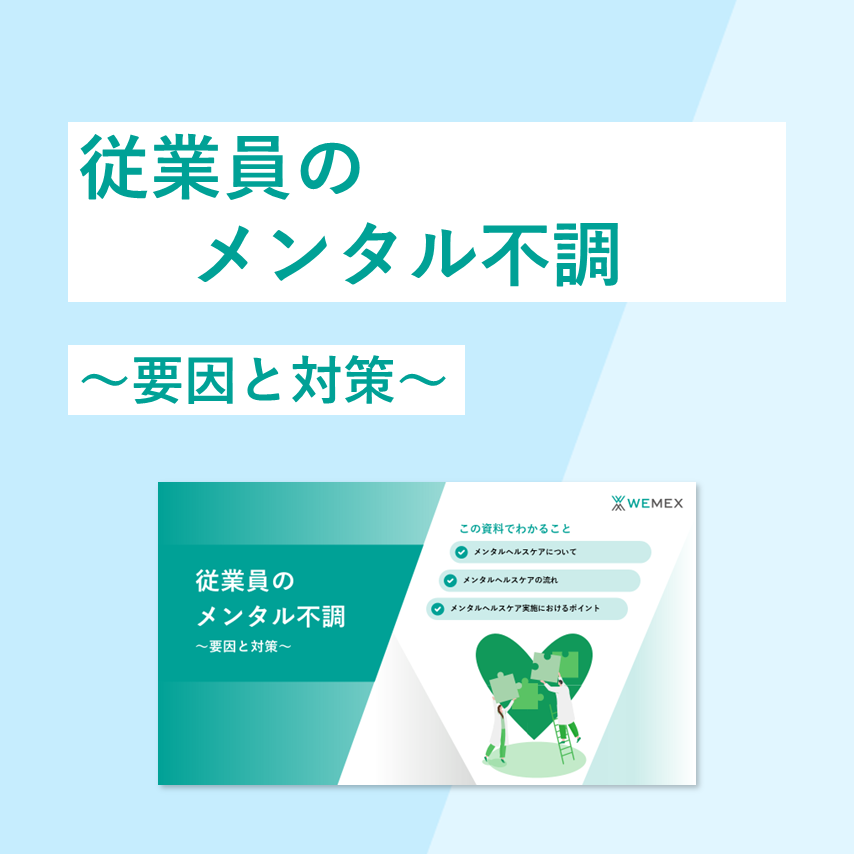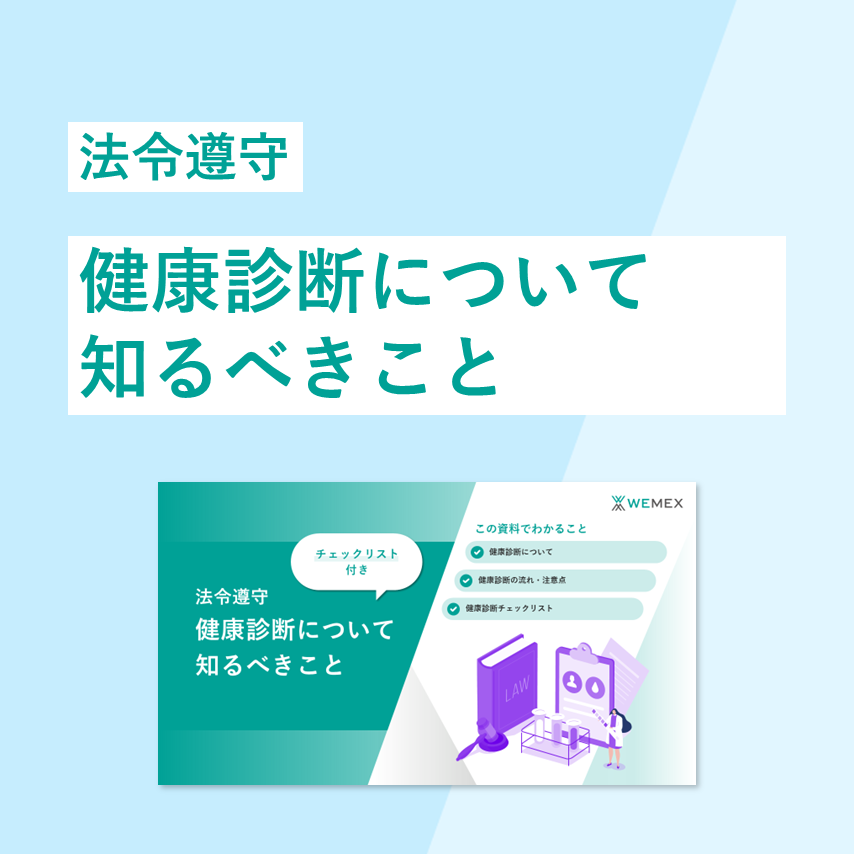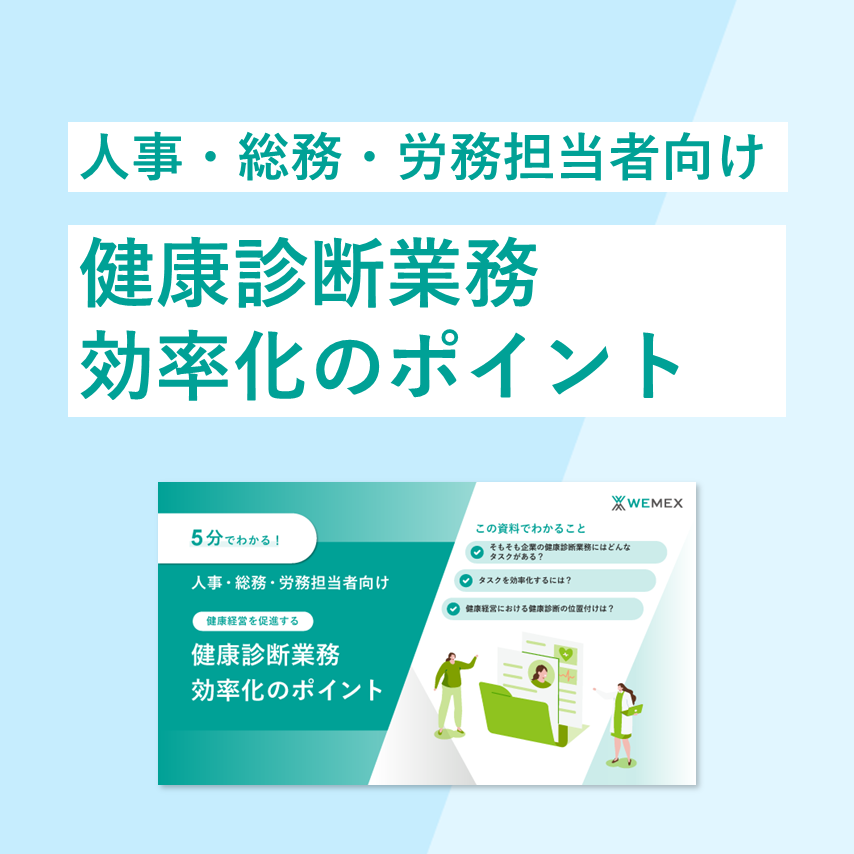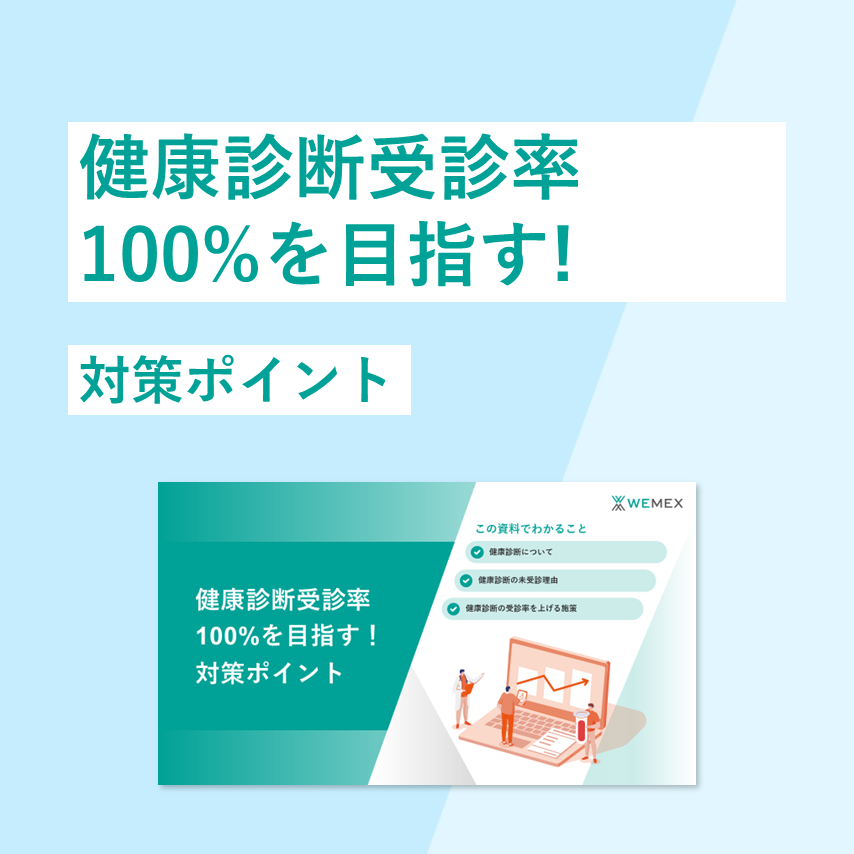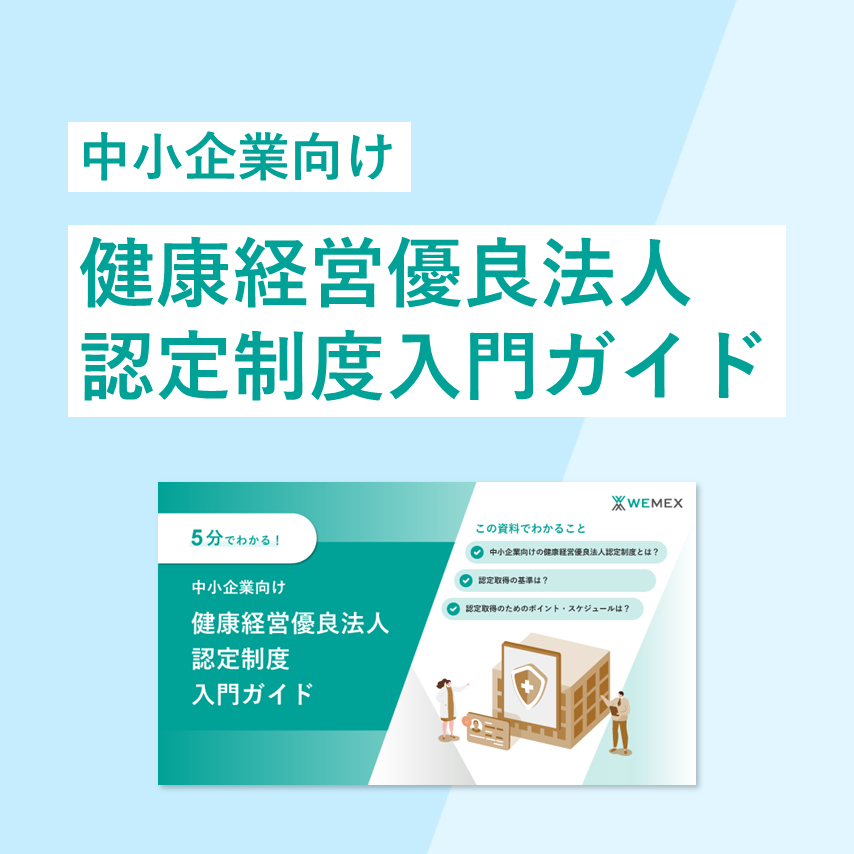目次
健康診断の再検査とは
健康診断の再検査は、「二次検査」や「精密検査」と混同されることもあります。ここでは、再検査がどのような検査を指すのか、二次検査や精密検査との違いを併せて解説します。

二次検査の一種
再検査は二次検査の一種であり、健康診断で異常所見が見られた従業員に対して、同じ項目をもう一度実施する検査を指します。異常な数値が一時的なものかどうかを確認することが目的です。
二次検査の中でも再検査は、異常の程度が比較的軽い場合に対象となります。治療が必要な段階ではないため、過度な心配は不要です。生活習慣の乱れや一時的な体調変化などが原因で、数値が一時的に正常値を外れることも少なくありません。
関連記事:健康診断は会社の義務!目的や内容・罰則について解説
精密検査との違い
精密検査も二次検査の一種ですが、再検査よりも異常の程度が大きい場合に実施されます。異常な数値が一時的とは考えにくいため、異常の原因を特定することが目的です。
精密検査では、通常の健康診断や再検査よりも詳しい検査が行われます。がんなどの深刻な疾病を早期に発見できる可能性もあるため、非常に重要な検査です。
再検査や精密検査を受診する医療機関と費用負担
再検査や精密検査は、対象となる従業員が限られているため、通常の健康診断とは扱いが異なります。ここでは、受診する医療機関の選択や費用負担の取り扱いについて解説します。
医療機関は従業員が自由に選べる
再検査や精密検査を受診する際の医療機関は、基本的に従業員が自由に選ぶことができます。一般的には、最初に健康診断を受けた医療機関で再度受診するのがスムーズです。また、かかりつけ医で受診するケースも多く、既往歴や体質を把握してもらっているため安心感があります。
企業側に費用負担の義務はなし
通常の健康診断と異なり、再検査や精密検査にかかる費用については、企業側に負担義務がありません。基本的には従業員の自己負担となります。ただし、企業によっては福利厚生の一環として費用を補助または全額負担している場合もあります。
自己負担の場合、受診をためらう従業員も少なくありませんが、企業が費用を補助することで受診率が向上する可能性があります。
健康診断の事後措置とは
企業は健康診断を実施しただけで終わりではなく、異常所見がある従業員に対して「事後措置」を実施しなければなりません。事後措置は労働安全衛生法第66条により企業へ義務づけられており、従業員の早期治療や健康リスクの低減を目的としています。
企業が適切に事後措置を実施することで、異常所見のある従業員が健康を回復できるケースもあります。事後措置は、健康診断そのものと同等、場合によってはそれ以上に重要な取り組みといえるでしょう。
事後措置として企業が対応すること
事後措置を適切に実施するためには、対応内容を正しく把握しておく必要があります。ここでは、企業が健康診断後に行うべき主な事後措置を解説します。
従業員への結果の通知
健康診断の結果を実施機関から受領したら、各従業員に通知します。その際、異常所見の有無も必ず確認しましょう。異常所見とは、測定値が基準値を超えている項目を指します。異常の程度によって区分が分けられますが、その区分や名称は実施機関によって異なります。
再検査や精密検査の受診勧奨
異常所見のある従業員には、再検査や精密検査の受診を促します。声かけやメール送信などが一般的な方法です。自主的に受診しない従業員もいるため、受診勧奨は重要な対応となります。ただし、受診は従業員の義務ではなく、強制することはできない点に注意が必要です。
関連記事:受診勧奨とは?重要性や実施基準やポイントを紹介
産業医への意見聴取
異常所見があった従業員については、産業医へ報告します。従事している業務内容などの情報も提供し、医学的な観点から就業継続の可否や必要な措置について意見を聴取します。従業員数が50人未満の場合は産業医の選任義務がないため、他の医師や地域産業保健センターへの意見聴取が代替手段となります。
就業上の措置
産業医などの意見をもとに、異常所見のある従業員に対して「通常勤務」「就業制限」「要休業」のいずれかの措置を講じます。
- 通常勤務:特別な措置を行わず、従来どおりの業務を続ける。異常所見が軽度な場合に選択
- 就業制限:休憩時間の増加、勤務時間短縮、作業内容変更などを行う
- 要休業:休職して健康状態の回復を図る。復帰を前提に実施され、異常所見が重度の場合に選択
就業制限や要休業では、従業員に不利益や不当な取り扱いとならないよう配慮が必要です。
従業員との面談
就業制限や要休業の判断を下した場合、対象従業員との面談を行います。人事担当者のほか、産業医にも同席してもらい、その判断の理由や背景を説明します。従業員の意見を聴き、納得を得たうえで措置を実施するのが望ましいです。また、生活習慣の改善指導も併せて行うことで、健康回復の促進につながります。
関連記事:産業医面談とは?内容やメリット・注意点を解説
企業に求められる法的義務

健康診断後の事後措置において、企業には複数の法的義務が定められています。ここでは、企業が遵守すべき主な義務の内容を確認していきましょう。
個人結果の保存
健康診断の結果は、従業員ごとに個人票を作成し、5年間保存することが義務づけられています。保存方法は紙でも電子データでも問題ありません。電子管理であれば、保管スペースが不要になり、検索や管理の効率化にもつながります。
保健指導の実施
保健指導は、労働安全衛生法第66条の7に基づき、健康診断で異常所見が見つかった従業員を対象に産業医や保健師が行うものです。就業上の措置が不要な「通常勤務」と判定された場合でも、保健指導の対象となります。従業員の生活スタイルや健康状態を踏まえた支援を行うことが重要です。
では、保健指導で具体的にどのような内容が実施されるのか見ていきましょう。
生活習慣改善のための指導
異常所見の多くは日常生活の習慣が原因です。そのため、飲酒や喫煙、睡眠など、生活リズムの見直しに関する指導を行います。たとえば、飲酒量を減らす目標の立て方や喫煙を控える工夫、十分な睡眠を確保するための習慣づくりなど、無理なく続けられる改善方法を提案します。
食事に関する指導
食生活は健康状態を大きく左右し、検査値にも反映されます。異常所見が見られる場合は、栄養バランスの偏りが原因であるケースが多いため、現状の食生活を見直すサポートを行います。具体的には、栄養バランスを意識した食事構成や、カロリー・塩分摂取の適正化、食材の選び方などについて助言します。これにより、栄養面への意識を高め、健康的な食習慣の定着を目指します。
運動に関する指導
適度な運動を習慣化することは、健康維持に欠かせません。保健指導では、運動の重要性を伝えるだけでなく、楽しみながら継続できる方法を提案します。たとえば、通勤時に徒歩時間を増やす、休日に軽い運動を取り入れるなど、日常生活に無理なく組み込める工夫を紹介します。運動不足が異常値の原因となっている場合でも、継続的な運動により改善が期待できます。
就業判定
就業判定は、労働安全衛生法第66条の5に基づく義務で、異常所見のある従業員に対して、産業医が医学的な観点から就業の可否や制限の必要性を判断するものです。一般的には、産業医への意見聴取と同時に実施されます。
判定時には当年度の健康診断結果だけでなく、過年度のデータも参考にします。数値の推移や過去の異常傾向を考慮し、総合的な判断を行うことが重要です。
労働基準監督署への報告
従業員が50人以上の事業場では、労働基準監督署への健康診断結果報告が義務づけられています。報告書は所定の様式に基づき、厚生労働省のウェブサイトから作成可能です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/)
事後措置を実施するうえで押さえておくべきポイント
健康診断後の事後措置を適切に進めるためには、重要なポイントを理解しておく必要があります。以下に、企業がとくに注意すべき点をまとめます。
保健指導や再検査に難色を示す従業員への対応
保健指導や再検査は従業員の健康維持を目的としていますが、必ずしも全員が受診に前向きというわけではありません。受診勧奨を行っても、難色を示すケースがあります。
特保健指導は法的に「努力義務」とされており、未実施に対する直接的な罰則はありません。しかし、実施しなかったことで従業員の健康状態が悪化した場合、安全配慮義務違反として企業が責任を問われる可能性があります。そのため、拒否理由をヒアリングし、業務調整や時間確保など受診しやすい環境づくりに努めることが重要です。併せて、受診による健康面のメリットを丁寧に伝えることで、受診率向上が期待できます。
従業員にとって不利益な対応は禁止
健康診断の結果を理由に従業員へ不利益な扱いをすることは厳禁です。たとえば、異常所見があったことを理由に退職勧告や契約更新拒否を行うこと、または就業上の措置を口実に不当な配置転換を行うことは認められません。
就業上の措置は、産業医の意見聴取を経たうえで、従業員の健康保護を目的に実施するものです。企業の都合を優先した不当な利用は避けなければなりません。
プライバシーへの配慮
健康診断および事後措置では、従業員の個人情報を扱う場面が多くあります。情報漏洩を防ぐため、取り扱いには細心の注意が必要です。
紙の書類は施錠可能な保管場所を利用し、電子データはパスワード管理やアクセス権設定を行い、担当外の従業員が閲覧できないようにしましょう。また、管理担当者は最小限の人数に絞ることで、情報管理のリスクを低減できます。
まとめ
健康診断後の事後措置は企業に義務づけられており、従業員の健康を守るうえで欠かせない取り組みです。再検査や精密検査の受診に消極的な従業員もいますが、受診しやすい環境を整え、積極的に受診を促すことが重要です。適切な保健指導を実施すれば、従業員の健康状態が改善する可能性も十分にあります。
ウィーメックスでは、企業向けに健診代行サービスを提供しています。健診機関との契約手続きから進捗管理、結果の電子化まで、健康診断に関する業務の約90%を削減可能です。事後措置もスムーズに実施できる体制を整えておりますので、ぜひこの機会にお問い合わせください。