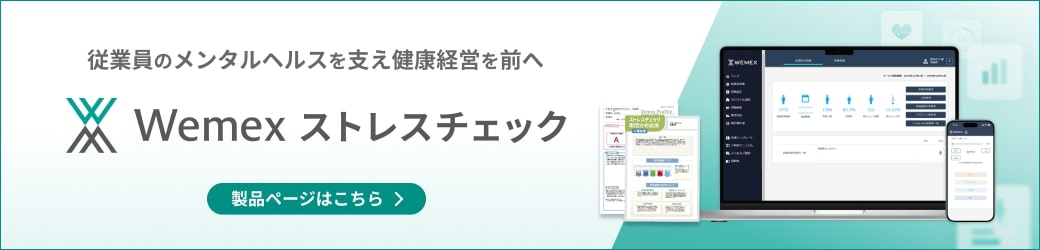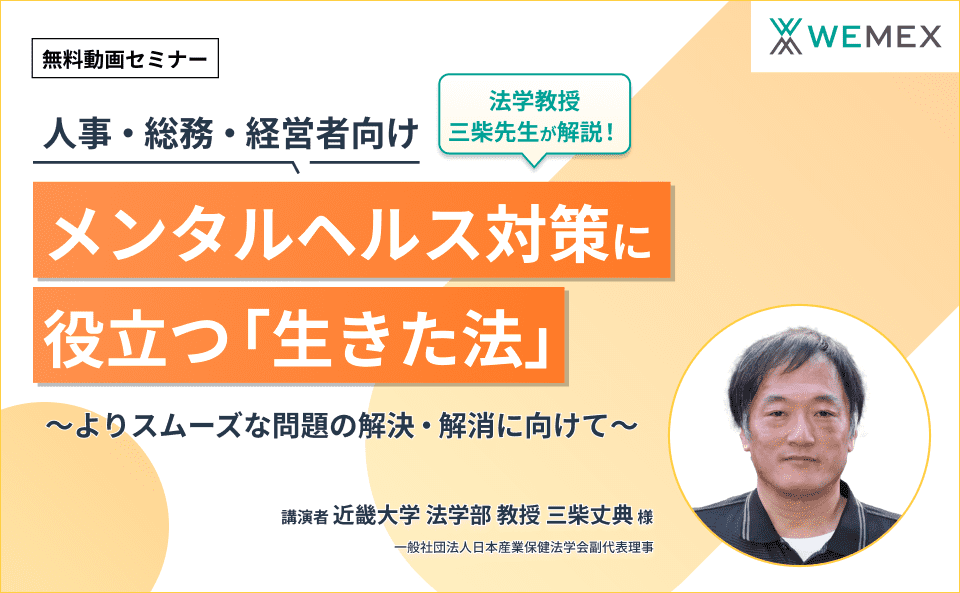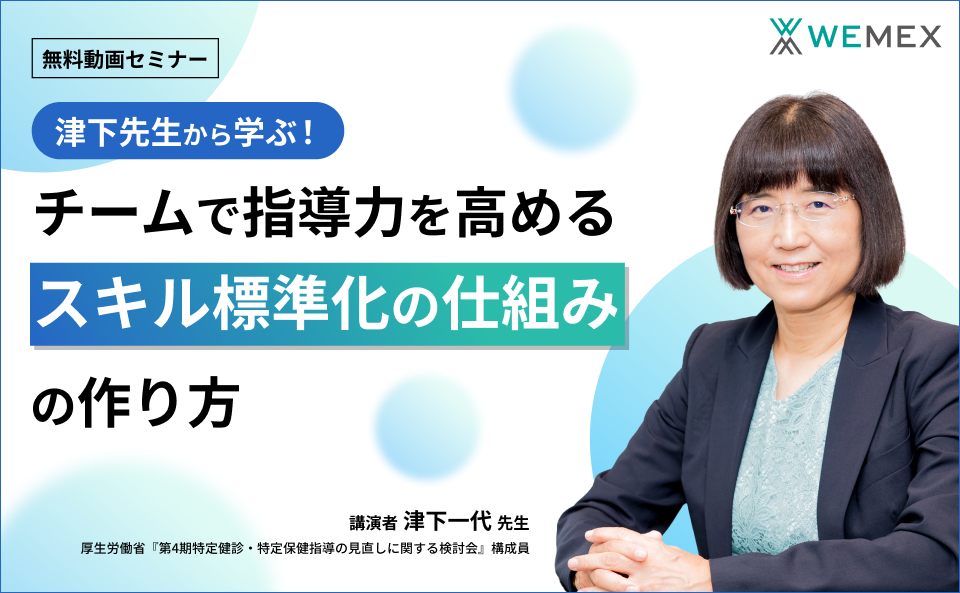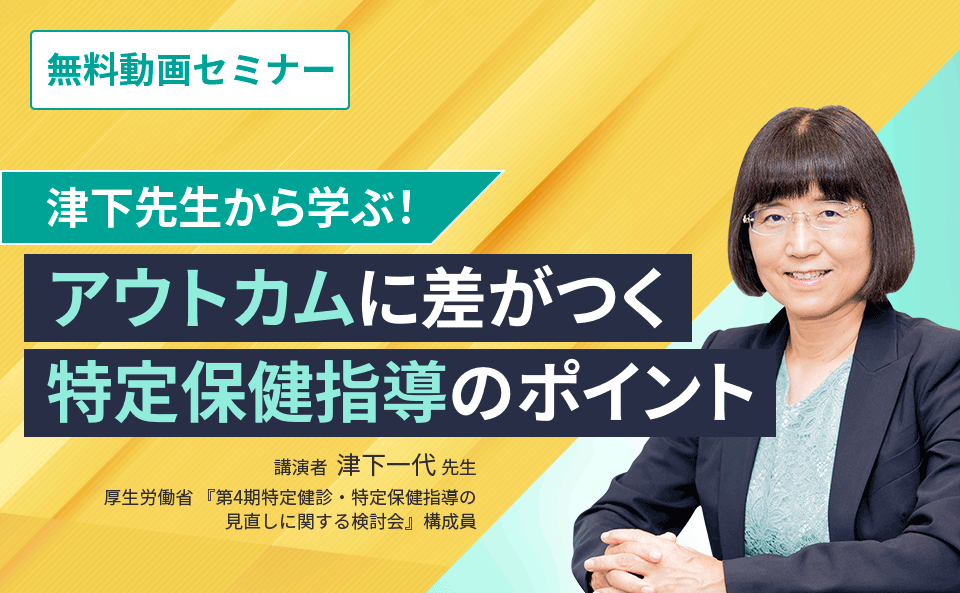目次
PHRとは
PHR(Personal Health Record:パーソナル・ヘルス・レコード)とは、個人の健康に関する情報を一元的に記録・管理する仕組みを指します。医療機関の受診歴、検査結果、既往歴、アレルギー情報、健康診断の結果、生活習慣データなどがPHRの代表的な内容です。
PHRの特徴は、医療機関が管理するのではなく、「個人が自らの健康データを主体的に管理」する点にあります。データはクラウド上に保存され、スマートフォンアプリなどを通じて容易に記録・確認が可能です。日常の健康計測データをアプリで記録している場合も、それはPHRの一形態といえます。

EMRやEHRとの違い
PHRと混同されやすい概念として、EMRやEHRがあります。いずれも医療・健康関連のデータを扱いますが、目的や管理主体が異なります。以下でその違いを整理します。
EMRとは
EMR(Electronic Medical Record)は、紙のカルテを電子化した「電子カルテ」を指します。医療機関内部で使用され、医師や看護師などの医療従事者が診療記録を作成・閲覧します。
原則としてEMRは医療機関内で管理され、医療従事者が診療記録を作成・閲覧するために利用されます。ただし、現在は電子カルテ情報の共有を進める取り組みが進行しており、今年度中に運用が開始される「電子カルテ情報共有サービス」を通じて、患者本人が自らのカルテ情報を確認できるようになる予定です。
EHRとは
EHR(Electronic Health Record)は、「電子健康記録」と呼ばれる仕組みです。診療や治療に関するデータに加えて、患者の健康に関わる幅広い情報を含んでいます。
EHRは複数の医療機関が診療や健康データを連携して活用することを前提とした仕組みであり、主に医療従事者によって運用されます。ただし、EMRと同様に、今後は国の「電子カルテ情報共有サービス」などの仕組みにより、患者本人が自らの健康・医療情報を参照できる機会が拡大する見込みです。
したがって、現時点では企業がEHRを直接利用することは想定されていないものの、将来的には個人を介して健康管理への活用が進む可能性があります。
PHRの分類
PHRは、大きく「公的なシステムを利用するもの」と「民間企業が提供するサービスを利用するもの」に分類できます。ここでいう公的なシステムとは、主にマイナポータルを指します。以下では、マイナポータルと民間PHRの違いを見ていきましょう。
マイナポータル
マイナポータルには、過去の健康診断結果や予防接種履歴などの医療データが記録されています。ログインして「健康医療」という項目から入ると自分の情報を閲覧できます。また、医療機関によっては、感染症やアレルギーなどの情報も記録されます。
ただし、利便性や機能性は健康管理専用に設計されたものではなく、日常的な健康管理目的での活用にはやや不便を感じる場合があります。
民間PHR
民間PHRは、個人が自分の健康管理に活用することを目的として提供されるサービスです。主にスマートフォンアプリやWebブラウザから利用できます。
マイナポータルとの大きな違いは、健康情報を記録し、見やすく整理・表示できる機能が充実している点です。日々の数値変化を詳細に記録し、グラフ表示などで視覚的に確認することも可能です。提供される機能はサービスごとに異なります。
PHRが健康経営に活用できる理由
PHRは健康経営の推進において非常に有用なツールです。ここでは、なぜPHRが健康経営に活用できるのか、その主な理由を解説します。
数値を用いた取り組みができる
PHRには、従業員の健康データが数値として蓄積されます。これらのデータを収集・分析することで、客観的な根拠に基づいた施策の立案が可能です。部署ごとの傾向をグラフ化すれば、組織全体の健康状態を可視化し、部門ごとの課題を洗い出せます。
また、個人単位でも活用できます。PHRデータから健康リスクの高い従業員を早期に発見し、必要な対策を講じることで、健康管理をいっそう強化することが可能です。
健康意識を高めるきっかけをつくれる
企業が従業員にPHRアプリを提供することで、日常的にデータ閲覧や記録を行う習慣が生まれます。自身の健康データを見る機会が増えると、自然に関心を持ちやすくなり、健康意識の向上につながります。
こうした意識変化によって、食生活の改善や運動習慣の開始など、行動に移す従業員が増え、生活習慣病の予防に直結します。
健康診断後の事後措置の実施に役立てられる
健康診断後には再検査が必要な従業員もいますが、再検査は義務ではないため受診が進まないケースがあります。PHRアプリを利用すれば、健康診断や再検査の受診状況を正確に把握でき、未受診者へ直接受診勧奨を行うことも可能です。
さらに、保健指導の場でもPHRデータを活用することで、より個別性の高い効果的な指導を行えます。
関連記事:受診勧奨とは?重要性や実施基準やポイントを紹介
事務処理の工数を削減できる
多くのPHRアプリはデータ自動記録機能を備えており、手作業による入力の手間を削減します。データ取得後すぐにシステムへ反映されるため、入力作業にかかる時間と労力を削減できます。これにより、人事や健康管理担当者の事務負担が大幅に軽減されます。
健康経営優良法人の調査項目に設けられている
2025年から、「PHR活用促進」が健康経営優良法人の調査項目に追加されました。現時点では必須ではないものの、導入している企業は認定取得に有利となります。
とくに「ホワイト500」や「ブライト500」ではPHR活用が重視されており、将来的に必須要件となる可能性もあります。認定取得を目指す企業にとっては導入が望ましい取り組みです。
関連記事:【2026年度版】健康経営優良法人の変更点と認定取得のポイント
PHRを活用した企業の取り組みの例

健康経営にPHRを導入・活用する際には、他社の事例を参考にすることが有効です。以下に、PHRを効果的に活用している企業の取り組み例を紹介します。
ICTツールの見直しでPHRの利用拡大
ある企業では、以前からPHRサービスを導入していたものの、従業員の登録率は40%台にとどまっていました。そこで、利用しやすさを向上させるためにICTツールの見直しを実施。その結果、登録率が65%まで上昇しました。
さらに、登録率が70%を超える店舗や部門に追加ポイントを付与するインセンティブ制度を導入し、利用促進を図っています。PHRの活用を通じて従業員の健康意識も高まり、ウォーキングラリーなどの健康イベントへの参加率は従来の3倍に増加しました。
AI健康アプリとの連携で活用
別の企業では、従業員にAI健康アプリを提供し、PHRデータと連携させて活用しています。これにより詳細なデータ分析が可能となり、より効果的な健康管理を実現しています。
法人向けPHRアプリを使えば、企業全体や部署ごとの健康データ分析が可能となり、健康経営施策の立案に役立ちます。
近年では、ESG投資の一環として健康経営に取り組む企業も増加。短期的にはコストがかかっても、従業員の健康維持・増進による中長期的な利益を重視する動きが広がっています。
アメリカ企業での取り組み
アメリカでは1992年、心理学者ロバート・ローゼン博士の著書『The Healthy Company』をきっかけに健康経営の概念が普及し始めました。現在では、優秀な人材の確保に健康経営は不可欠であり、PHRの活用に注力する企業が多数存在します。
一部の企業では、従業員の48%が企業提供のヘルスケアアプリを利用しており、主要な健康情報を記録・追跡できる機能が充実。多様なアプリ連携が行われ、PHRデータの高度な活用が進んでいます。
関連記事:健康経営とは?メリットや取り組み方を解説
PHRを活用した取り組みを行う際の課題
PHRを活用した取り組みには多くの利点がありますが、導入・運用にあたってはいくつか注意すべき課題も存在します。以下では、主な課題と留意点を解説します。
導入目的を明確化する
PHRアプリは多種多様で、機能や対応できるデータの種類も異なります。導入目的に合致しないアプリを選んでしまうと、十分に活用できない可能性があります。
まずは、自社の健康経営における課題や今後の方針を整理した上で、目的に沿ったアプリを選定することが重要です。PHRの導入はあくまで健康経営を実現するための「手段」であることを忘れないようにしましょう。
十分なセキュリティ対策
PHRには非常にセンシティブな個人情報が含まれます。従業員の中には、自分のデータが外部に知られることに強い抵抗を持つ人もいます。万一情報が漏洩すれば、企業の信頼低下につながりかねません。
そのため、情報漏えいや不正アクセスへの対策など、堅牢なセキュリティ体制の構築は必須です。
従業員の心理的抵抗感への対処
PHRデータの登録や共有に抵抗を感じる従業員も存在します。このような場合、アプリを配布しても利用が進まないことや、登録率の伸び悩みが想定されます。
対応策としては、プライバシー保護や利用目的について丁寧な説明を行い、理解と同意を得ることが重要です。利用を強制せず、あくまで本人の意思を尊重する姿勢が求められます。
従業員のITリテラシー格差への対処
PHRアプリを効果的に利用するには一定のITリテラシーが必要です。ITが苦手な従業員は利用へのハードルを高く感じる場合があります。
多くの従業員に活用してもらうためには、サポート体制の整備や研修・説明会の実施が有効です。とくに高齢層が多い職場では操作性の高いアプリを選び、必要に応じて個別指導を行うことも検討しましょう。
健康投資の効果検証の仕組みづくり
PHRを活用した施策導入後、すぐに期待どおりの効果が得られるとは限りません。継続的な効果検証の仕組みを整えることで、成果や課題を明確にできます。検証結果をもとに施策を改善し続けることで、より高い健康経営効果を実現できます。
まとめ
健康経営にPHRを活用することで、従業員の健康意識向上や人事担当者の業務負担軽減が期待できます。また、健康経営優良法人認定の取得にも有利に働きます。まだ導入していない企業も、この機会に検討してみてはいかがでしょうか。
なお、ウィーメックスでは企業向けに健診代行サービスを提供しています。健診機関との契約から結果の電子化まで、健診業務を一括でお任せいただけます。ぜひこの機会にお問い合わせください。
メディコム 人気の記事
イベント・セミナーEVENT&SEMINAR
お役立ち資料ダウンロード
-

健康経営 人事・総務
【最新法令対応】健康診断実施業務ガイドブック2025年改正に基づく電子申請義務化対応を解説
-
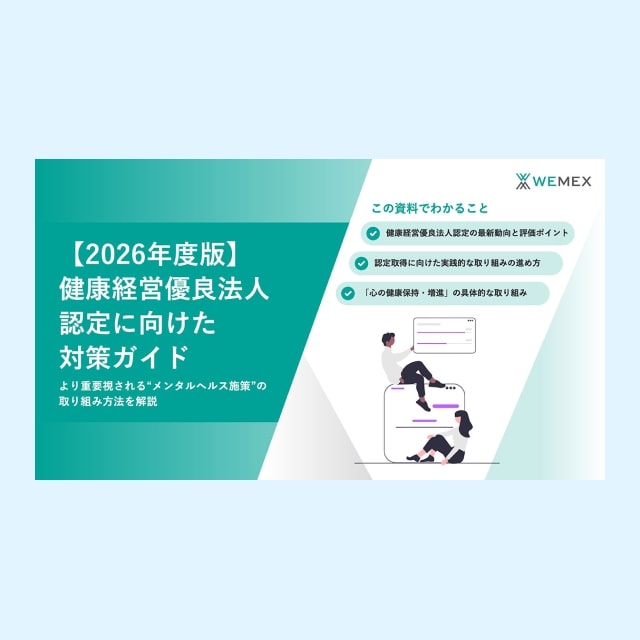
健康経営 人事・総務
【2026年度版】健康経営優良法人認定に向けた対策ガイド
-
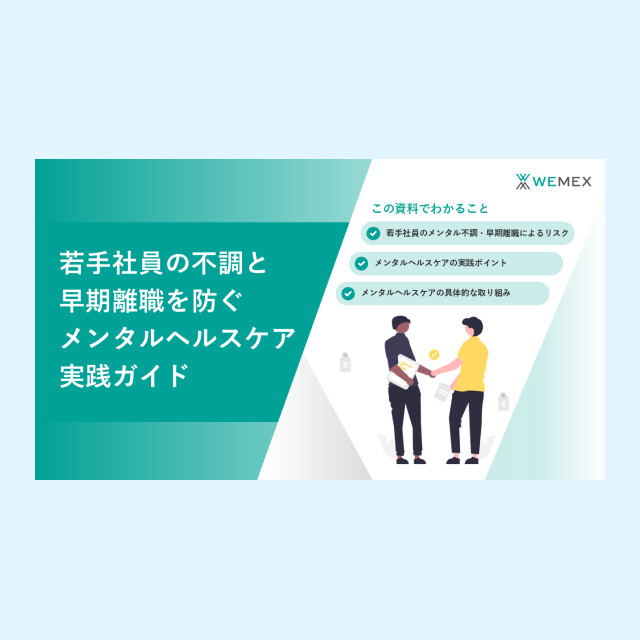
健康経営 人事・総務
若手社員の不調と早期離職を防ぐメンタルヘルスケア実践ガイド
-
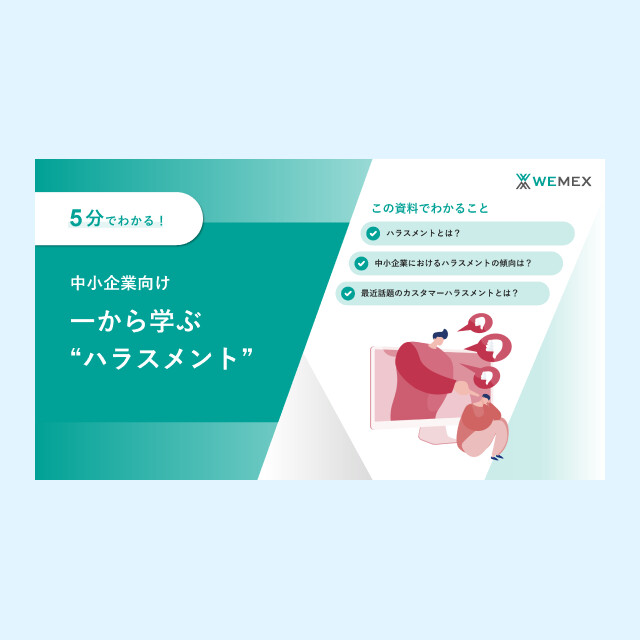
健康経営 人事・総務
中小企業向け 一から学ぶ“ハラスメント”
-
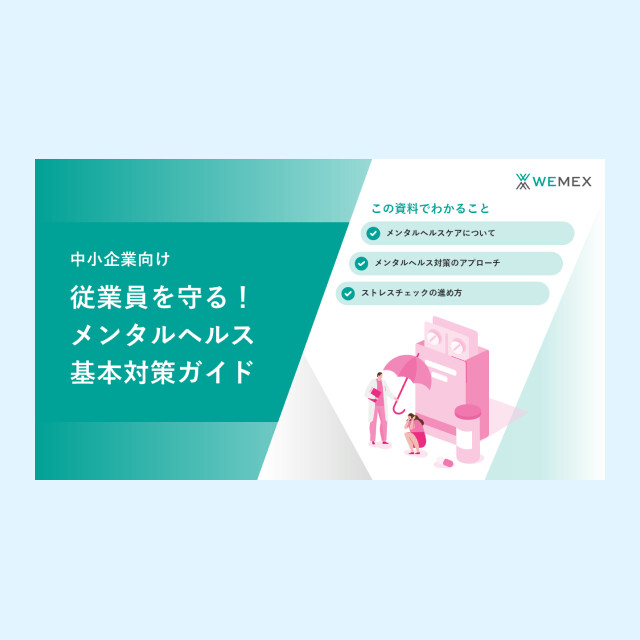
健康経営 人事・総務
中小企業向け 従業員を守る!メンタルヘルス基本対策ガイド
-

健康経営 人事・総務
従業員のメンタル不調~要因と対策~
-

健康経営 人事・総務
法令遵守【チェックリスト付き】健康診断について知るべきこと
-
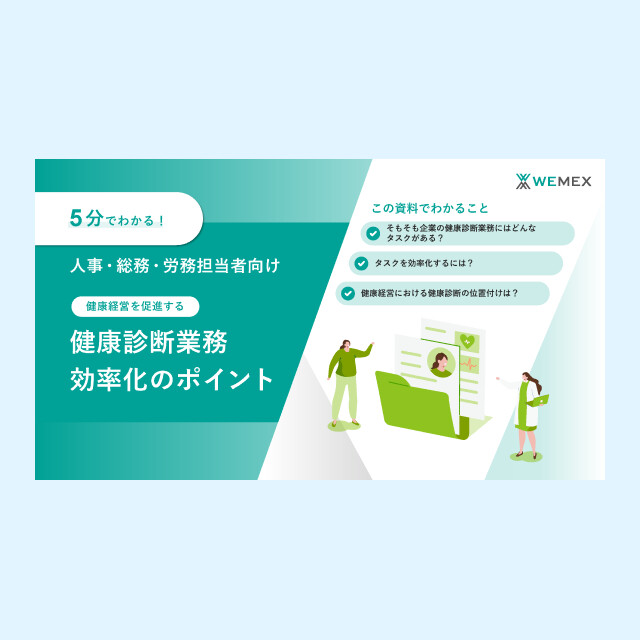
健康経営 人事・総務
健康経営を促進する健康診断業務効率化のポイント