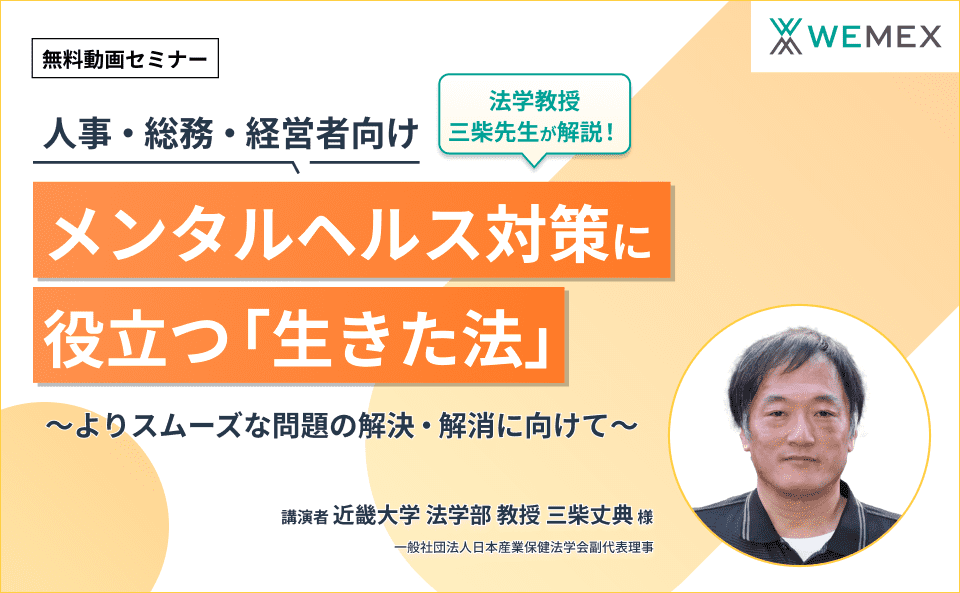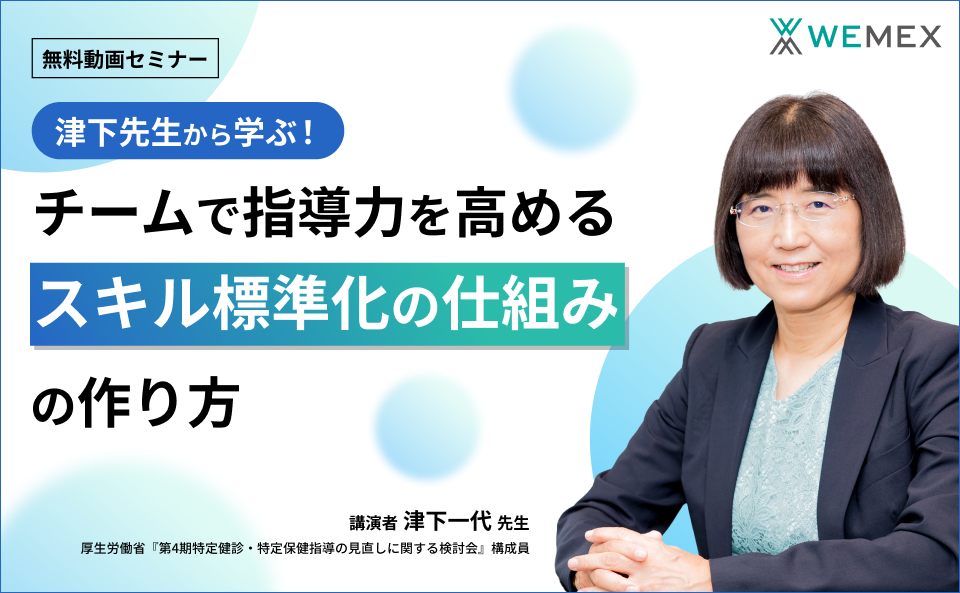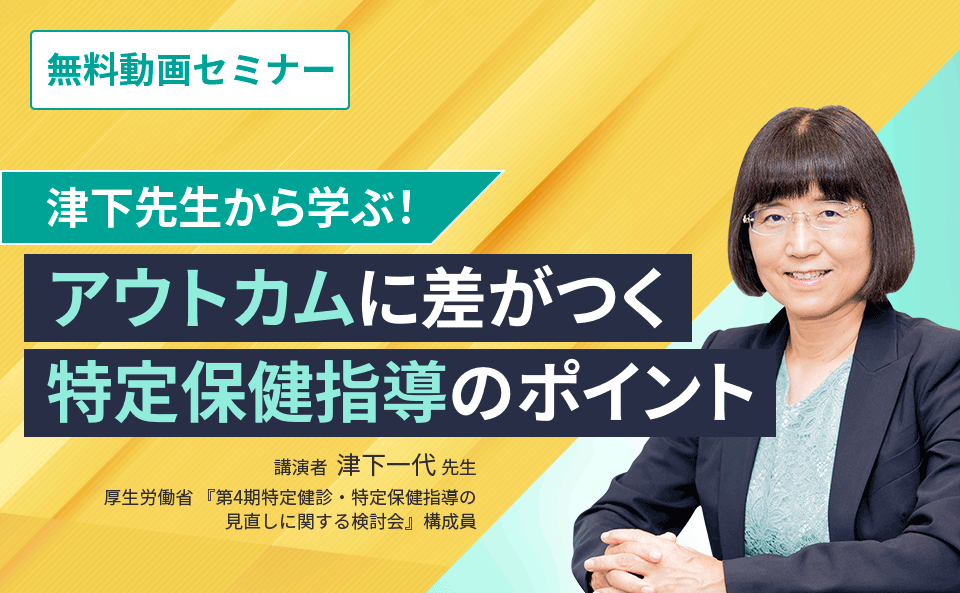目次
特定健診とは
特定健診は、正式には「特定健康診査」と呼ばれ、通常の健康診断と似ている部分も多くあります。ただし、その運用方法には違いが見られます。ここでは、具体的にどのような点が異なるのかを見ていきましょう。

実施主体
通常の健康診断は、企業に対して実施が義務づけられています。一方で、特定健診は健康保険の「保険者」に実施義務があります。保険者とは、健康保険組合や協会けんぽなどを指します。
企業は特定健診の直接的な実施義務者ではありませんが、保険者から協力を求められることがあります。人事部門が保険者と連携を取ることで、特定健診の円滑な実施が可能になります。
対象者
通常の健康診断は企業で雇用している全従業員が対象となり、年齢制限はありません。これに対し、特定健診の対象は「実施年度の4月1日時点で40歳以上75歳未満の被保険者およびその被扶養者」です。
また、通常の健康診断は従業員に受診義務がありますが、特定健診の受診は「任意」とされています。従業員も被扶養者も、希望すれば受けられる仕組みです。
通常の健康診断との違い
特定健診は、通常の健康診断と完全に別のものではなく、多くの検査項目が共通しています。主な違いは、「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」リスクの判定に重点を置いている点です。このため、メタボリックシンドロームに関わる検査項目が追加されています。
さらに、一定の基準に該当する人には、より詳細な検査(心電図、眼底、貧血、腎機能など)が行われる場合もあります。
共通する検査項目については、通常の健康診断と重複して受ける必要はありません。通常の健康診断を受けていれば、足りない項目だけを追加で受けることで対応が可能です。そのためには、保険者が企業から健康診断結果を受け取っておく必要があります。
生活習慣病のリスクが高いと判断された場合
特定健診の結果、生活習慣病のリスクが高いと判断された被保険者や被扶養者には、「特定保健指導」が実施されます。特定保健指導では、保健師や栄養士などの専門職が生活習慣の見直しや改善をサポートします。
支援内容はリスクの程度に応じて、
- 動機付け支援
- 積極的支援
の2段階に分かれます。
この特定保健指導も、特定健診と同様に受けるかどうかは本人の任意です。
関連記事:特定保健指導の実施率向上に効く!対象者判定から実施まで効率化のポイント
特定健診の流れ
ここでは、特定健診を実施する際の主な流れについて順を追って解説します。
委託先の選定
特定健診は、通常、外部の健診機関に委託して行います。まずは、委託先となる健診機関を選定しましょう。ただし、特定健診の委託には厚生労働省が定める「委託基準」があり、この基準を満たしている健診機関を選ぶ必要があります。
対象者への通知・案内
委託先が決定したら、特定健診の対象となる従業員およびその被扶養者に対して、通知や案内を行います。案内方法としては、メールや社内文書の送付、パンフレット配布などが一般的です。
通知には以下の情報を明記しておくと良いでしょう。
- 予約方法
- 実施場所や日時
- 持ち物や注意事項
これらを丁寧に案内することで、対象者が安心して受診できる環境を整えられます。
特定健診の実施
案内を受け取った従業員や被扶養者は、案内に従って健診機関へ予約を行います。事前に送付された問診票に必要事項を記入し、当日会場に持参して受診する流れが一般的です。健診は保険者の指定方法に従って実施されます。
判定・結果の通知
受診後、一定期間を経て保険者のもとに結果データが届きます。保険者は結果をもとに判定を行い、
- 個人票の作成
- 結果の郵送や電子通知
- 特定保健指導の対象者判定(動機付け支援・積極的支援の振り分け)
を実施します。
なお、特定保健指導の対象でない場合でも、結果に基づいて健康維持や生活習慣改善につながる情報提供を行うことが望まれます。
特定健診の受診率
2023年度の最新データによると、特定健診の実施率は全体で59.9%にとどまっており、およそ4割の人が受診していない状況です。これは、通常の健康診断と比較しても低い水準となっています。
また、健康保険の保険者ごとに受診率には大きな差があります。
- 健康保険組合・共済組合:おおむね80%前後と高水準
- 協会けんぽ:50%台とやや低め
さらに、被保険者と被扶養者を比較すると、その差はいっそう顕著です。被扶養者の受診率は、健康保険組合・共済組合でも40%台程度にとどまり、協会けんぽでは20%台と非常に低い水準となっています。
このように、被扶養者の受診率の低さが、全体の平均を押し下げる要因となっています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001492020.pdf)
特定健診を受診しない場合の主な理由
生活習慣病予防のためには特定健診の受診が望ましいものの、さまざまな理由から受診しない従業員や被扶養者もいます。ここでは、その代表的な理由を紹介します。
時間的余裕がない
特定健診を受診するには、一定の時間を確保する必要があります。業務が多忙な場合、受診の優先度が低くなり、そのまま見送られることも珍しくありません。
被扶養者の場合も、家事や育児に追われ受診の時間を作れないケースがあります。健康に大きな問題がないと感じている人ほど、時間を割いてまで受診しようとは思いにくい傾向があります。
受診場所や時間が不便
受診会場までのアクセスが悪いと、足が遠のく要因になります。自宅から遠かったり交通の便が悪かったりすると億劫に感じられやすいです。また、受診可能な曜日や時間帯が限られる場合、都合が合わず受診を断念することもあります。
必要性を感じていない
現時点で健康に不安がない人は、「特定健診を受けなくても問題ない」と考えることがあります。自覚症状がないうちは健康問題を軽視しがちで、「不安を感じたときに医療機関を受診すればよい」と考える傾向があります。
良くない結果が出るのが怖い
健康状態に不安があるにもかかわらず、「悪い結果と向き合いたくない」という心理が働き、受診を避ける人もいます。自分の健康問題が客観的に証明されることを恐れ、現実から目を背ける行動です。しかし、この場合、将来後悔する可能性が高くなります。
特定健診の受診率向上のための施策
従業員や被扶養者の生活習慣病予防を支援するためには、特定健診の受診率向上が重要です。ここでは、そのために有効な具体策を紹介します。
受診しやすさを追求した環境整備

従業員や被扶養者が受診しやすくなるよう、環境を整えましょう。
- 交通アクセスの良い場所にある健診機関を選定する
- 複数の健診機関から選べる体制を整える
また、勤務時間中の受診を許可したり、受診のための特別休暇制度を設けたりすることで、忙しさを理由に受診を見送っている従業員にアプローチできます。
受診者に特典を付与
受診者に健康関連グッズを配布するなどの特典を用意するのも有効です。健康への関心が低い層にも、受診のきっかけを提供できます。さらに、部署単位で受診率を競い、上位部署を表彰する施策も効果的です。チーム意識を活用し、受診意欲を高められます。
受診勧奨を実施
対象でありながら未受診の従業員には、リマインドを行いましょう。文書送付だけでは効果が限られるため、電話やメールなど双方向でのコミュニケーションを加えると効果が高まります。
また、未受診の理由をヒアリングし、それに応じたサポートを行うことで、受診してもらえる可能性をさらに高められます。
関連記事:受診勧奨とは?重要性や実施基準やポイントを紹介
特定健診の受診率向上で得られるメリット
特定健診の受診率を高めることで、企業や従業員双方に以下のようなメリットがあります。
生活習慣病の早期予防
40歳以上になると、肥満・高血糖・脂質異常・高血圧などのリスクが高まり、心筋梗塞や脳梗塞といった重篤な疾病の危険性も増します。リスクが高い状態に気づかず生活を続けると、突然の発症による入院や、生活への深刻な影響を招く可能性があります。
特定健診の受診によって、これらのリスクを早期に把握し、予防対策を取ることができます。これは将来的な医療費削減にもつながります。
生産性向上
健康状態は業務パフォーマンスに直結します。体調不良では高い成果を出しにくく、上司や同僚に負担を与えることにもなります。一方で健康状態を良好に維持できれば、パフォーマンスの向上や欠勤・休職リスクの低減が可能です。これは本人だけでなく、職場全体に良い影響をもたらします。
健康経営優良法人での評価向上
健康経営優良法人の評価項目には、特定健診および特定保健指導の実施率が含まれています。実施率が高い企業は評価が上がり、認定取得に有利です。認定を得ることで企業の社会的信頼性が向上し、取引先からの高評価や事業推進の優位性につながります。
特定健診に関して人事担当者が知っておくべき法律
特定健診は法律に基づいて実施されており、人事担当者は関連法令への理解が求められます。ここでは、特定健診に携わる際に押さえておきたい法律について解説します。
特定健診の根拠となる法律
特定健診の実施は「高齢者の医療の確保に関する法律」第20条に規定されています。具体的な検査項目や運用方法は厚生労働省令で定められています。
さらに、特定健診・特定保健指導の受診率が低い場合には、後期高齢者医療支援金の加算対象となる仕組みがあります。保険者の負担増により、健康保険料率の引き上げが必要となる可能性もあります。したがって、企業としても受診率向上に取り組む意義は大きいといえます。
特定健診に関わる罰則
特定健診に関連しては、秘密保持が第30条で義務化 されており、167条に罰則が定められています。罰則内容は「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です。特定健診では多くの個人情報を扱うため、取り扱いには細心の注意を払い、法令遵守のもと業務を行う必要があります。
まとめ
特定健診は、従業員やその被扶養者の生活習慣病予防において非常に重要な取り組みです。健康経営優良法人の認定や後期高齢者医療支援金の算定にも影響するため、企業としても受診率向上は大きな課題となります。受診率が低い場合は、受診しやすい環境の整備や特典の付与など、積極的な対策を講じましょう。
また、健診業務をアウトソーシングすることで、特定保健指導の対象者を迅速に抽出でき、結果的に従業員の健康維持に直結します。
ウィーメックスでは健診代行サービスを提供しており、対象者への案内や未受診者への受診勧奨まで包括的に対応可能です。人事担当者の業務負担を軽減しつつ、受診率向上につなげられます。この機会にぜひお問い合わせください。
メディコム 人気の記事
イベント・セミナーEVENT&SEMINAR
お役立ち資料ダウンロード
-

健康経営 人事・総務
【最新法令対応】健康診断実施業務ガイドブック2025年改正に基づく電子申請義務化対応を解説
-
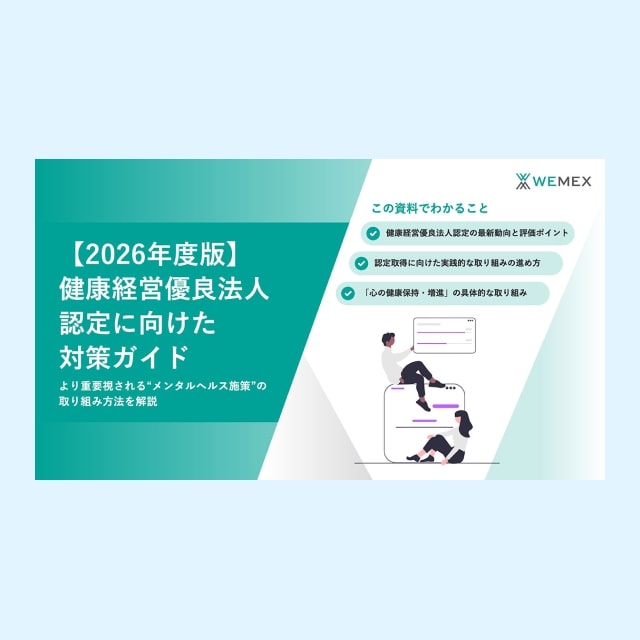
健康経営 人事・総務
【2026年度版】健康経営優良法人認定に向けた対策ガイド
-
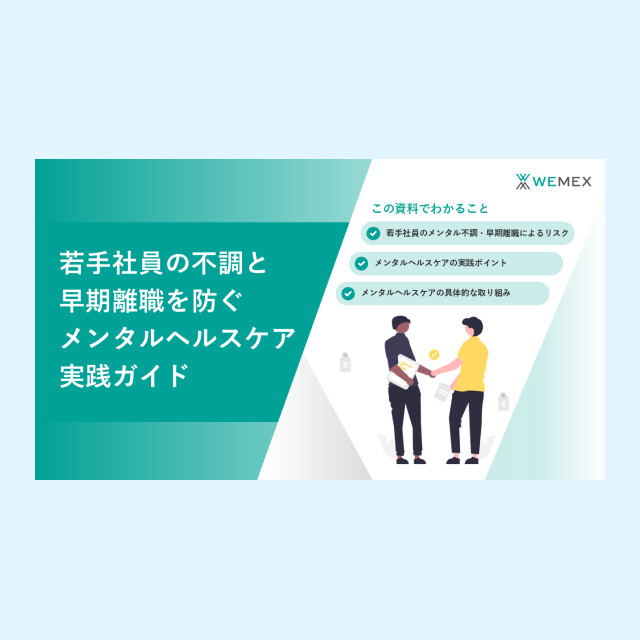
健康経営 人事・総務
若手社員の不調と早期離職を防ぐメンタルヘルスケア実践ガイド
-
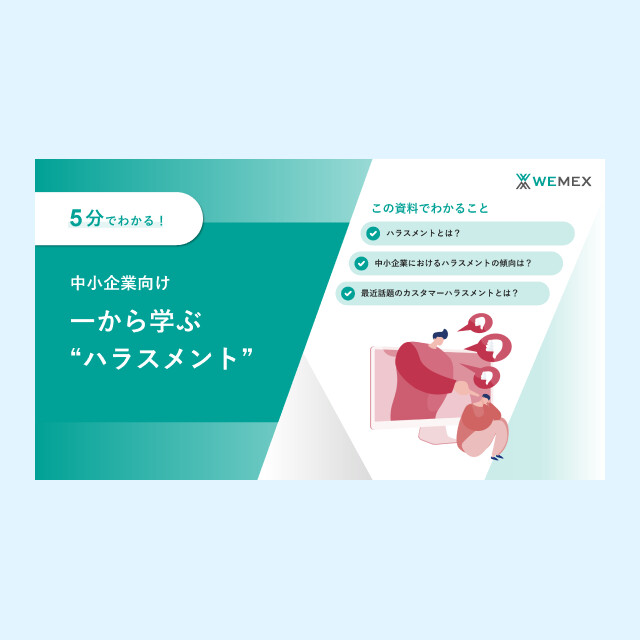
健康経営 人事・総務
中小企業向け 一から学ぶ“ハラスメント”
-
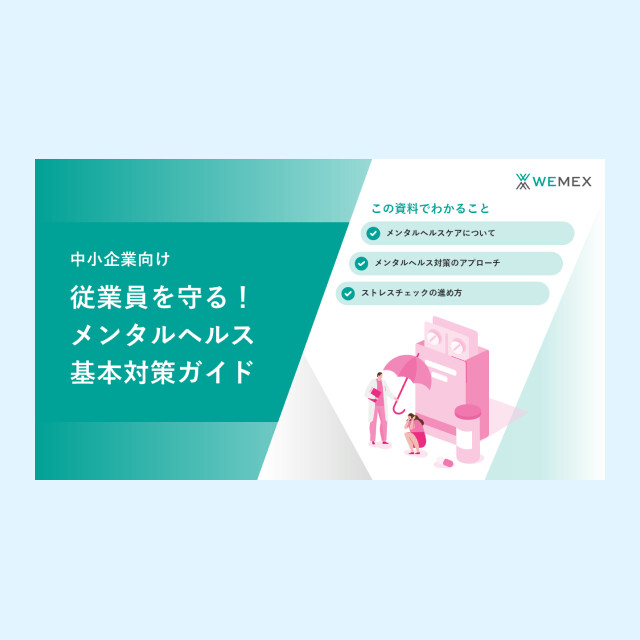
健康経営 人事・総務
中小企業向け 従業員を守る!メンタルヘルス基本対策ガイド
-

健康経営 人事・総務
従業員のメンタル不調~要因と対策~
-

健康経営 人事・総務
法令遵守【チェックリスト付き】健康診断について知るべきこと
-
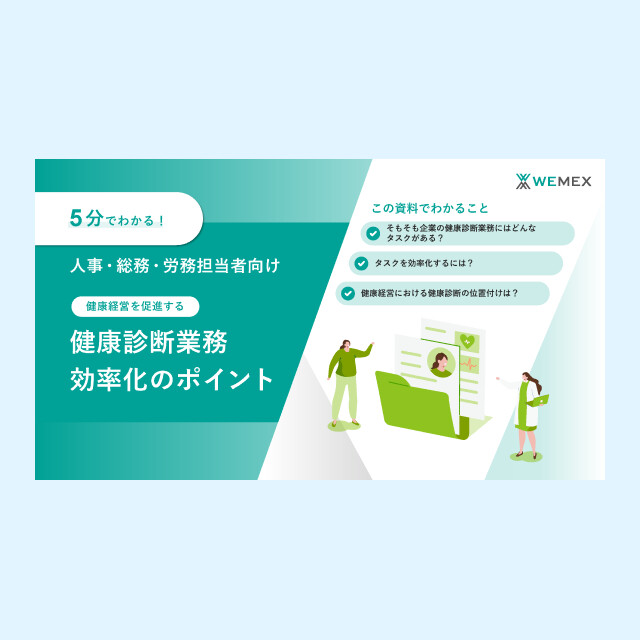
健康経営 人事・総務
健康経営を促進する健康診断業務効率化のポイント