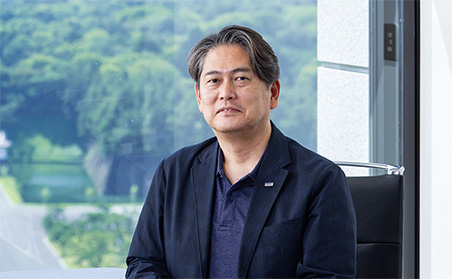ヘルスケアの未来を切り拓く人財育成と、
個々の自律的な成長が持続する組織づくりを目指して
- 平嶋 竜一
- PHCホールディングス株式会社
専務執行役員
最高総務責任者(CAO)
最高人事責任者(CHRO)
最高変革責任者(CTO)
1. 人的資本戦略:経営と人事を結ぶ成長戦略
新ビジョン・価値観をベースに経営戦略・人事戦略を同期させながら各取り組みを推進し、企業価値向上を図る
私は、従業員一人ひとりの成長がグループ全体の発展と企業価値向上に不可欠だと考えています。「中期経営計画2027」とともに、新たに策定したビジョンと価値観を基盤に、人事戦略と経営戦略を同期させることで、両者の相乗効果により経営目標を達成し、従業員エンゲージメントを高め、企業価値の向上につなげたいと考えています。そこで、「中期経営計画2027」では、人事戦略として、多様な才能と可能性を最大限に引き出す環境づくりを進めています。
2. 人事戦略の具体的な取り組み
当社は、人事戦略として、従業員エンゲージメントの向上を目指しつつ、持続的な成長を人財面から牽引することに注力しています。この戦略の狙いは、多様な個性を持つ従業員一人ひとりがそれぞれの強みを最大限に活かして活躍できる環境を築き上げることであり、次の3つの施策を主に推進しています。1つ目は、各自の能力開発を促す人財育成、2つ目は、人事関連業務のデジタル化を進める人事DXの推進、そして3つ目は、会社への貢献意欲や愛着を高めるエンゲージメントの向上です。これらの人財施策を通じて、当社はさらなる成長を目指しています。
人財育成
当社では、未来を担う次世代リーダーの育成に注力するとともに、すべての従業員が主体的に学び続ける企業文化を醸成しています。個人の成長と組織の発展を両輪で推進し、誰もが働きがいを感じられる環境を整備することで、企業価値の向上と社会への貢献を目指します。
-
次世代リーダーを育成「PHCアカデミー」開講
将来の経営を担うリーダーの輩出に向けて、当社は、2024年に「PHCアカデミー」を立ち上げました。このアカデミーは、PHCグループ全体で次世代の経営層やリーダーを育てるための研修プログラムのことで、シニアマネジメントを対象とした「Potential Successor Candidate」と、次世代層の「Next Generation」の2つの階層で構成されています。当社は、このアカデミーでの継続的な幹部育成を通じて、持続可能な組織運営を目指しています。「Potential Successor Candidate」に国内外から選出された20名は、2024年1月から約1年半にわたる研修に参加しました。この研修では、「中期経営計画2027」に掲げられた新しいビジョンや価値観を踏まえつつ、知識の習得だけでなく、リーダーとしての思考力や変化を起こす力、変革推進力を高め、グループ全体でのネットワーク形成も促進します。
この夏の研修では、オムロン株式会社を訪問し、代表取締役執行役員副社長CTOの宮田喜一郎様からオムロンの経営理念等についてご講演いただきました。また、オムロン ヘルスケア株式会社代表取締役社長の岡田歩様からは、オムロン ヘルスケアのこれまでの歩みと目指す姿についてご講演いただきました。本取り組みは、単に自社内の議論にとどまらず、我々がお手本とする企業から、経営理念の浸透や新規事業の立ち上げ、成長戦略等について、積極的に学んでいくということが狙いです。
また、このアカデミーの育成プログラムは、論理的思考、サイエンスを担う左脳を鍛えるMBAのような科目学習にとどまりません。右脳的要素である芸術、文化、歴史から学ぶリベラルアーツの要素も重視しています。社外の有識者・山口周氏による講演などを通じて、アートとサイエンスについての理解を深め、将来の経営を担うリーダーとしての見識を深めてもらうことも目的としています。
-
グループ共通研修:学び続ける組織へ
当社では、将来を担うリーダーの育成に力を入れるだけでなく、全社的な育成体系を構築するなど、すべての従業員のスキルアップも重視しています。一人ひとりが自ら積極的に学び、現在の仕事の範囲にとどまらず、新しい知識やスキルを習得する文化を築き上げることが当社には不可欠だと考えています。このような自律的な学習を促し、個人の成長を支援する文化が根付くことで、組織全体がより強くしなやかになると確信しています。
具体的な取り組みとして、まずグループ全体の管理職・リーダー層を対象とした「リーダーシップ研修」を実施しています。この研修では、マネジメント能力、部下を育成する力、公正な評価スキル、労務管理の知識を高め、これらを実際の業務で確実に実践できるようサポートしています。また、全従業員が共通して身につけるべき知識やスキルについては、グローバル人事プラットフォームを活用して提供しています。さらに、外部の学習プラットフォームも導入し、各自の課題に合わせて自由に学べる環境を整えています。
人事DXの推進による、公平な機会の提供を追求
当社はまた、従業員の誰もが成長し、公平な機会を得られる企業文化を大切にしています。具体的には、グローバル共通の人事システムを導入し、全従業員のスキルや経験を、集約して管理しています。本システムには、従業員各自の多岐にわたるスキルや経験を基としたデータベースを構築し、異動や配置、昇進などを決める際に、データと論理的な根拠に基づいた説明ができるようになっています。誰にどの仕事を任せるか、どのような研修がその人の成長に役立つのかを明確な根拠とともに示すことで、より公平で透明性の高い、戦略的な人事マネジメントを実践しています。このように、グローバル共通の人事システムを導入し公平な人事を行うことで、やる気を高め、当社が大切にする「個を尊重する企業文化」をさらに強固にしたいと考えています。
こうした人事DXの推進においては、単にシステムを導入するだけでなく、活用することにも力を入れています。エンゲージメントを測る調査など、さまざまな取り組みを同じシステム上で行い、データを一元的に管理しています。また、各自が積極的にシステムを利用し、自分のキャリア形成に役立てられるよう、実践的な研修プログラムも多数提供しています。システムが本当に役立つためには、一人ひとりが主体的に使うことが不可欠だと考えており、使いやすさと便利さの追求に努めています。
エンゲージメントの向上
-
職場環境改善:働きがいを高める環境づくり
当社は、従業員が安心して働き、意欲を持って挑戦できる土壌づくりを最も重要な基盤と考え、さまざまな取り組みを進めています。従業員が自信を持って働けるよう、心理的安全性の確保や称賛し合う仕組みの構築を通じて、働きがいと学びへの意欲の醸成を図っています。年度単位で定期的に行うグローバルエンゲージメントサーベイに加えて、組織状態のタイムリーな可視化を目的に、簡素な質問で構成するパルスサーベイを今期から新たに実施しています。この結果を踏まえて、現場での対話とアクションにつなげています。
具体的な施策として、CEOが人事部門やIR・広報部と連携し、従業員向けのタウンホール・ミーティングやラウンドテーブルといった場で全世界の従業員との直接対話を積極的に実施。タウンホール・ミーティングは月に1回、ラウンドテーブルは年間50回以上開催しています。これらの機会を通じて、従業員からは「CEOと直接話ができて、CEOの考えを直に聞くことは大いに学びとなり、とても良かった」「CEOから直接激励の言葉をかけられて嬉しかった」といった肯定的な声が多数寄せられています。特に海外の従業員は、会社の役員との対話の機会を重んじるため、こうした施策はとても有効と認識しています。
2024年度に行ったエンゲージメントサーベイの結果にも表れているように、従業員が成長を実感しづらい状況が過去数年間続いていました。これは、当社の業績が必ずしも成長しておらず、新製品のリリースも滞りがちであったことが一因と考えています。会社全体の成長と個人の成長は無意識のうちに結びつけて考えてしまうため、各自のモチベーションに大きく影響していました。そうしたこともあり、直近のエンゲージメントサーベイでスコアが向上したのは、業績の改善が大きく寄与していると分析しています。事業として目に見える成果を出すことは、従業員の不安を和らげ、安心感につながります。従って、事業そのものを強化していくことは、エンゲージメントの向上においても極めて重要であると認識しています。
また、PHCホールディングスとPHCの一部の本社機能を置く東京・日比谷オフィスにおいては、従業員のエンゲージメント向上と働きやすさを重視した取り組みを実践しています。フリーアドレス制を導入したこともあり、共有スペースでは、普段交流する機会があまりない部署の従業員と自然に会話が生まれ、偶発的なコミュニケーションが日常的に行われています。このオフィスには2024年4月に移転してきましたが、部署間の連携も深まり、組織全体の活性化を実感しています。私自身もオフィス選びに携わりましたが、眺望の良さも重要なポイントでした。遠くの景色を眺めてリフレッシュできる空間は、心身の健康維持に役立ち、ストレス軽減と生産性向上につながると考えています。このような快適なオフィス環境は、エンゲージメントを高めるために不可欠であり、サーベイで明らかになった課題への対応策の一つでもあります。
さらに、「ファミリーデー」の開催も検討しています。家族をオフィスに招き、普段の職場を見てもらうことで、家族の理解を深め、従業員のモチベーション向上を図りたいと考えています。
-
非財務情報(人的資本)の開示の強化
当社は、東京証券取引所のプライム市場へ上場する企業として、取引所が求める開示強化の要請に積極的に応えていきます。これまで開示の中心であった財務情報に加え、取引所や株主・投資家の皆さまからは、非財務情報の開示を強く求められています。統合報告書はその最たるものであり、非財務情報を積極的に開示してまいります。特に、人財や組織に関する情報は極めて重要であると認識しており、これらの開示を強化します。
-
One PHCの推進と多様性の尊重
当社は、現在の社長・出口が就任して以降、「One PHC」というスローガンを掲げ、グループ全体の結束力強化に努めています。これまで、過去に買収した企業の自律性や多様な経営のあり方を尊重する姿勢が強かった当社において、この「One PHC」の考え方、マインドは、グループの求心力を高める重要な指針となっています。
マネジメント層や幹部社員においては特に、相互の連携を強化し、円滑な相談ができる関係性を築くことが非常に大事です。先に述べた「PHCアカデミー」においても、人的ネットワーク形成を促進するべく、参加者同士の人財交流も積極的に推奨。2024年12月には、日本、アメリカ、スイスといった当社の主要拠点以外のオーストラリアに各事業の代表者が集結し、普段交流の少ないメンバー同士で活発な議論を交わしました。参加者からは、多様なバックグラウンドを持つメンバーとの交流が有益であったとのフィードバックが多く寄せられており、この取り組みは「One PHC」の意識醸成に大きく貢献していると実感しています。
一方で、すべての従業員が、あらゆる階層において完全に一体となることの難しさも認識しております。そのため、例えば、人事制度や報酬体系において、各事業の成り立ち、顧客基盤、製品特性に最適化された部分を無理に統一する必要はないと考えています。各事業が持つ独自の強みや多様性は、当社の成長において重要な要素と捉えています。
従って、「One PHC」の推進においては、まず比較的高い階層の従業員から、この理念への理解を深め、交流を促進していくことが合理的で、上層部からグループとしての意識を共有し、協力体制を築くことで、段階的に全社的な一体感が醸成されていくと私自身は考えています。

3. 今後の展望
個を尊重し、機会を均等に与える企業文化
当社は、度重なる買収を経て事業を拡大してきましたが、その過程において「どちらが買収し、どちらがされたか」といった視点ではなく、個人の尊重と機会の公平性を最も重視する企業文化を育んできました。
過去には、当社の源流である松下寿電子工業、あるいは買収した企業といった出自に関わらず、優れた能力と意欲を持つ人財がグループ全体のトップに就任しています。例えば、過去には、独バイエルから買収したアセンシア事業のトップが、当社のCEOに就いていた時代もあります。これは、会社の出自や国籍、年齢、性別に関わらず、能力と意欲があれば誰にでもチャンスがあるという当社の考え方を明確に示しています。もちろん、すべての従業員が社長を目指す必要はありませんが、一人ひとりの従業員に上限を設けず、誰もが自身の能力を最大限に発揮できる機会を提供していることは、当社の大きな誇りです。
独立性とグローバル展開が培う共創文化
当社がパナソニックグループからカーブアウトし独立した背景には、ヘルスケア専業企業として、自らが描く成長を追求したいという強い動機がありました。ヘルスケア事業の対象領域は広範にわたるものの、個々の分野は細分化された小規模な市場の集合体であり、国内事業だけでは収益を確保することが困難な構造にあります。このため、日本企業も海外企業も、グローバルな事業展開なくしては持続的な成長が実現できない共通認識を有しています。
このような事業環境において、当社は日本国内の視点にとどまらず、グローバルな市場で通用し、理解を得られる企業であるべきだと考えます。その根底にあるのは、多様な価値観を尊重し、共創を促す文化の醸成です。自身の業務範囲にとどまらず、部門や国境を越えて互いに関心を持ち、協働する姿勢を当社は重視しています。隣の席の同僚がどのような業務に携わり、どのような課題を抱えているのかに関心を寄せ、助け合い、声を掛け合うことで、組織全体のパフォーマンスを最大化できると信じています。
また、M&Aを通じて事業規模を拡大してきた経緯から、組織の縦割りや部門ごとの孤立が現在も問題視されることがあります。しかし、当社はこの状況を改善し、一人ひとりが好奇心を持って仕事に取り組む文化を育むことを目指しています。それは自社のことだけでなく、同業他社の動向、例えば研究開発部門であれば他社の新製品、経理・財務部門であれば他社の開示情報などに積極的にアンテナを張り、多角的な視点を持つことが重要です。常に広い視野を持ち、変化に対応できる組織へと進化していくことが、グローバル企業として不可欠であると考えています。
多様性の推進と公平な機会の提供
当社は、持続的な成長を実現するため、ESGの各側面において具体的なKPIを設定し、その進捗状況を開示しています。特に、女性管理職比率の向上は、当社の重要な経営課題の一つとして認識しています。現在、PHCグループの女性管理職比率は平均して20%台ですが、これを将来的には30%程度まで高めることを目指しています。
グローバルな視点で見ると、当社の海外子会社の中には女性管理職比率が約40%に達している企業もあり、管理職会議では女性がほぼ半数を占めます。一方、グループ全体では達成途上にあり、現状の改善は喫緊の課題です。性別に関わらず個人の能力が最大限に発揮される社会が理想であり、事業運営においても、女性からの視点が、製品開発や顧客サービスにおいて不可欠と認識しています。近年、この比率は改善傾向にありますが、さらなる向上に向けて努力を続けてまいります。
今後の展望
私は、「従業員一人ひとりの成長の総和が会社の成長」と捉えています。だからこそ、会社が人財に投資することを正当化できるのだと考えます。当社は、多様なバックグラウンドを持つ従業員がそれぞれの能力を最大限に発揮し、新たな挑戦を恐れない企業文化を醸成していきます。そして、お互いを尊重し、支え合い、ともに成長できる環境を提供することで、仕事に誇りを持ち、生き生きと働ける場所であり続けたいと願っています。
当社はこれからも、「わたしたちは、たゆみない努力で健康を願うすべての人々に新たな価値を創造し 豊かな社会づくりに貢献します」という揺るぎない経営理念を胸に、たゆまぬ努力と挑戦を続けてまいります。皆さまとともに、より健康で豊かな社会を創造していくことを心から楽しみにしています。
4. メッセージ:従業員の成長と誇りを育む企業を目指して
持続的成長を支える人財と組織機能の強化
私が理想とする会社の姿は、従業員が「どこに行っても通用する人財」でありながら、PHCグループで働くことを自らの意思で選択し、働き続ける会社となることです。他の企業で活躍できるような高い能力を持ちながら、当社で働くことに誇りとやりがいを感じてくれる環境を築きたいと考えています。
従業員が生き生きと働き、高いパフォーマンスを発揮するためには、「働きやすさ」と「やりがい」の掛け算が重要と捉えています。
そこで、従業員が一定のチャレンジに直面し、努力や頑張りを求められる一方で、人事に「サイエンス」を導入し、その努力が成果として結びつき、大きなやりがいを感じられる状況を創出することを目指しています。こうした働きやすさとやりがいが両立する環境こそが、エンゲージメントを高め、最終的に会社のパフォーマンス向上につながると確信しています。
最後に
私としては、一人ひとりが「PHCグループの役職員であること」を心から誇れる企業、毎晩「明日が来るのが待ち遠しい」と心から思えるような、ワクワク感に満ちた会社を目指しています。家族や友人にも自信を持って当社を紹介できるような、透明性と健全性を兼ね備えた組織でありたいと考えています。
また、当社は、従業員が自身の成長を実感できる環境づくりを重視しています。入社時には経験がなかった業務にも挑戦し、困難を乗り越える中で新たなスキルを習得し、できることが増えていく。そうした「個人の成長」と「会社の成長」が同じ方向を向き、互いに高め合う関係性を築くことが理想です。従業員が自身の成長を実感することで、会社への貢献意欲も高まり、より良い組織へと発展していくと信じています。